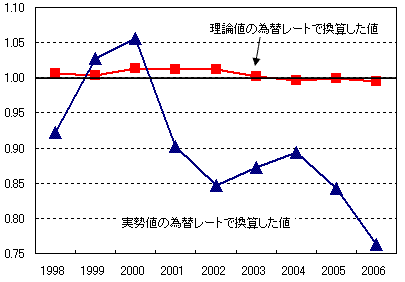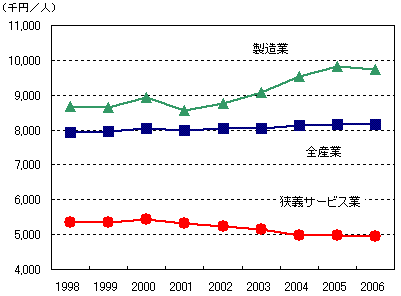| The World Compass(三井物産戦略研究所機関誌) 2008年7-8月号掲載 |
| 労働生産性から見る日本産業の現状 |
|
生産性がカギを握る。これは、個々の企業においても、経済全体の将来を展望するうえでも、間違いのないところだろう。とくに、人口減少時代に入り労働供給の制約が厳しくなるなか、労働生産性の動向は、これからの日本経済の行方を左右する最も重要なファクターの一つと位置付けられている。ここでは、労働生産性を切り口として、日本の産業の現状について考えてみたい。 労働生産性の日米比較−日本の労働生産性は低いのか?− はじめに、日本経済全体の労働生産性の現状を、米国との比較で概観しておこう(表1「GDP統計を用いた産業別労働生産性の日米比較」、別ウィンドウ表示)。ここでは指標として、2006年時点の産業別GDPをそれぞれの産業の就業者数で除した値を用いている(労働生産性の算出にあたっては、付加価値額を就業者数と平均労働時間の積である「労働投入量」で除すのが一般的であるが、ここでは日米のデータの基準をそろえるための便法として、就業者数で除した値を指標として使用している。生産性の指標については別掲1「物的生産性と価値的生産性」参照)。 政府も含めた全産業ベースで見ると、2006年の日本の労働生産性は、就業者一人あたり816万円で、同年中の平均の為替レート116円/ドルで換算すると7万ドルとなる。これは米国の9万2千ドルを1とすると0.76に相当する水準である。このデータで見る限り、日本経済全体としての生産効率は米国を大幅に下回っているという計算になる。しかし、同様の計算を2000年のデータで行ってみると、日本の労働生産性の対米国比は1.06と、日本が米国を上回っていたという結果が得られる。これをそのまま受け止めると、2000年から06年までの間に、日米のいずれか、あるいは双方で生産効率の大幅な変動があったように見えるが、実際には、そのような大きな変化が生じたとは考え難い。そうなると、両国の物価上昇率の差と為替レートの変動が影響している可能性が想起される。 そこで、両国の物価上昇率の差と為替レートの変動の影響を取り除くため、購買力平価の考え方で求めた各年の為替レートの理論値を用いて換算し直してみると、日本の労働生産性の対米国比は1998年から06年まで、1.01から0.99の間で安定的に推移している(下図、為替レートの理論値については別掲2「為替レートと購買力平価」参照)。
この結果から見ると、この間の日米両国の実質的な労働生産性はほぼ等しい状況が続いていたという結論になる。言い換えると、06年の日米の労働生産性に大きな差が生じているのは、日本の超低金利を背景とする極端な円安によるものであり、労働生産性の低下という表現から思い浮かぶような、生産活動の効率の大幅な低下が生じているわけではなさそうだ。 ただ、日本の労働生産性の対米国比(円・ドルの換算に理論値を使用したベース)が2000年の1.01から06年の0.99まで小幅とは言え低下していることには注意が必要だろう。これは、この間の日本の実質労働生産性の上昇率(表1で示した名目GDPベースの労働生産性の上昇率から物価上昇分を控除した値)が、米国を年率0.3%ポイント程度下回っていたことを意味している。この差は、労働力人口の増加率の差とともに、日本が2%前後、米国が3%弱と言われている経済成長の巡航速度、潜在成長率の差の一因を成している可能性がある。 産業別の労働生産性−サービス産業の生産性は問題か?− 次に、前掲の表1から、産業別の労働生産性の比較を見てみよう。日本においては、全産業の労働生産性を100とすると、製造業が119.4であるのに対して、金融・保険業が245.7、不動産業が764.9ときわめて高い値になっているものの、全就業者の35%を占める狭義サービス業は製造業のほぼ2分の1の60.6、同17%の卸売・小売業も78.6にとどまっており、サービス産業の多くの業種で生産性の低さが目立つ。 しかし、同様の傾向は米国でも見られる。そこで、産業別の労働生産性の対米国比を見てみると、製造業が1.00(円・ドルの換算に理論値を使用したベース)であるのに対して、広義のサービス産業が0.95、狭義のサービス業が0.93と、サービス産業の日米格差の方が若干大きくなっているものの、その差はとくに極端なものではない。そこから考える限り、労働生産性の業種間の格差は、設備の拡充や技術導入の遅れというよりも、いわゆる労働集約的な産業か資本集約的な産業かの違い、すなわち、それぞれの生産活動における人手による労働から資本設備の利用への置き換えの容易さを反映したものと言えそうだ(資本集約度の違いにともなう生産性の差を取り除く手法として、「全要素生産性、TFP=Total Factor Productivity」と呼ばれる考え方もあるが、実際の計測にあたっては、資本設備の価額の推計をはじめ、さまざまな仮定を置くことが必要で、それによって結果が左右されるうえ、資本設備の拡充と技術進歩とを切り離すことの意義は限られるため、ここでは扱わない)。 ただし、時系列で見ていくと、2001年以降、狭義のサービス業の労働生産性が低下基調となっており(下図)、その点には注意が必要だ。対米国比で見ても、2000年の1.04から06年には0.93まで低下している。
この動きは、この期間の日米間の生産性上昇率の差の主因となっている。その背景としては、この時期、サービス業においてパート比率が高まっていたことの影響が考えられる。表1では就業者の人数だけを分母として生産性を算出しているため、パート化が進んで個々の就業者の労働時間が短くなれば、生産性の値を押し下げる効果が生じる。また、従来のパートタイマーは、業務における技能や知識の水準が低い場合が多く、単に労働時間の短さ以上に生産性を押し下げている可能性もある。 パート比率の上昇にともなう労働生産性の低下については、人材を十分に活用できていないための現象という面がある一方で、フルタイムの就労機会しかない場合には労働力化しない層のマンパワーを労働市場に引き出すことで部分的ではあるが活用しているという面もある。ただ、いずれにしても、近時の傾向としては、パート化の流れが一巡しつつあることに加えて、パート労働力の一段の活用を目指して、労働時間の延長や技能の向上を図る企業が増えてきており、パート化にともなう生産性の低下には歯止めが掛かる可能性が高い。 次に、日本のGDP統計では内訳が公表されていないサービス業について、さらに細かく業種を分けて見てみよう。表2「法人企業統計(日)とGDP統計(米)を用いた産業別労働生産性の日米比較」(別ウィンドウ表示)は、サービス産業の生産性の日米比較をより細かい業種について行うために、日本側のデータとして、表1で使ったGDP統計に代えて、法人企業統計を用いて計算したものである。個人企業がカバレッジから外れているため、とくにサービス業の場合には、産業、業種の全体像と乖離している可能性もあるが、それを踏まえたうえで、それぞれの業種の生産性の対米国比を業種間で比較してみると、日本の産業の現状について、いくつかの仮説が浮かび上がってくる。 まず表1の算出結果と比較するために製造業の対米国比の値を見てみると、円・ドルの換算に理論値を使用したベースでも0.80と、GDP統計同士で算出した1.00よりもかなり低めの値になっている。それを踏まえてサービス産業の各業種の状況を見ていくと、小売業(0.90)、娯楽業(1.04)、飲食業(1.15)、教育・学習支援業(1.16)、生活関連・その他(1.38)は製造業を上回っており、運輸業(0.81)と宿泊業(0.79)はほぼ製造業並み、それ以外の卸売業(0.57)、情報通信業(0.53)、広告・その他の事業サービス業(0.53)、医療・福祉(0.56)は製造業を大幅に下回っている。 このうち、製造業を上回っている業種は、いずれも、人手を使った消費者向けサービスの性格が色濃い業種である。これらの業種においては、日本では競争激化を背景にサービスの高度化で消費者を引きつけようという方向性が目立っているのに対して、米国では情報システムを活用して業務を定型化し、賃金水準の低い未熟練労働力を人海戦術的に投入することでコストを削減しようという方向性が顕著で、それが付加価値ベースの労働生産性を押し下げる方向に働いている可能性がある。 一方、対米国比の数値が製造業に比べて低い業種では、知識集約的な事業への取り組みの度合いが日米の生産性格差の要因となっていると考えられる業種が目立つ。米国においては、卸売企業が小売企業の物流管理や商品戦略の策定を支援・代行する事例が多くなっている。情報通信業では、単なる情報交換の手段を提供するだけでなく、それをベースにさまざまなサービスや情報を提供するITビジネスが生み出されてきている。事業サービス業では法務関連や会計、経営コンサルタントなど、労働生産性の高い知識集約的なビジネスが日本に比べてはるかに成長している。 こうして業種別の状況を見てくると、付加価値で計る労働生産性を左右しているのは、必ずしも生産性という言葉でイメージされる生産効率の高低だけではないことが明らかになる。主たる業務や機能が似ているために同じ業種に分類されていても、ビジネスモデルや付随的な機能によって、労働生産性はまったく違った水準になり得る。日米間の業種別の労働生産性の格差には、そうした事業内容の違いの影響が大きくなっている可能性が高い。日本において業種全体として効率性に問題があるのは、ITの活用の遅れが指摘されている医療・福祉の分野や、ほとんど産業として扱われていない農業など、ごく一部の業種に限られそうだ。 産業構造の変化と生産性 これからの時代に、日本経済が成長していくには、労働生産性の向上が不可欠なファクターであることは間違いない。その点は労働生産性の定義式(下記)からも明らかだ。 労働生産性=GDP/(就業者数×平均労働時間) したがって、 GDP=労働生産性×(就業者数×平均労働時間) 人口減少時代に入り就業者数は停滞し、いずれは減少に転じる可能性が高い。個々の労働時間を延ばすにも限界がある。労働生産性が向上しない限りGDPの成長はあり得ない。 ただ、ここで注意が必要なのは、労働生産性が向上すれば必ずGDPが成長するとは限らないということだ。上の式によれば、労働生産性が向上した分、失業が拡大したりパート化が進展したりといった形で労働投入が減少し、GDPの増加には結び付かない事態も考えられるからだ。既存の市場の多くが飽和している日本経済の現状を考えると、たとえ労働生産性が向上しても、そうした縮小均衡に向かう可能性は十分ある。これから日本経済を成長させていくには、労働生産性を向上させるだけでなく、新たな需要と市場を創出していくことが必要だ。生産性の向上と新たな需要の創出は、いわば、経済を成長させるための両輪ということになる(需要創出の方向性については、08年2月付けレポート「日本産業の方向性−集中と拡散がうながす経済の活性化−」参照)。 労働生産性向上の原動力は、生産技術の進歩と、それを体現した資本設備と人材の拡充、高度化である。この点は、将来も変わることはないだろう。ただ、経済全体で見ると、産業構造の変化も労働生産性の変動に密接な関係を持っている。かつては、農業から製造業へのシフト、さらには製造業のなかでも労働集約的な業種から資本集約的な業種へのシフトといった、生産性の低い産業から高い産業への重心の移動を基調とする産業構造の変化が、経済全体としての生産性を押し上げる要因となっていた。日本の高度成長期が、その最も顕著なケースと言えるだろう。しかし、その変化が一巡すると、今度は逆に、製造業から生産性の低いサービス産業にウェイトが移るサービス化の流れが生じ、それが全体としての生産性の抑制要因となってくる。現時点では、日本や米国を含む多くの先進国が、そのような局面に入っている。 そうしたなかで今後の労働生産性の向上に向けたカギとなるのは、米国の卸売業や情報通信業、事業サービス業で見られるような知識集約的な事業と、コンテンツやソフトウェアなどの情報創造型の事業への移行だろう。とくに情報創造型の事業は、現行の統計では独立した業種としては扱われていないが、ITの飛躍的な高度化とインターネットの浸透によって情報流通のコストが劇的に低下したことで、音楽でも映像でも、人を引き付けるコンテンツさえあれば、限りなくゼロに近いコストで無数のユーザーに情報を販売し、莫大な付加価値を生み出すことが可能になっている。その場合には、当然、労働生産性も相当な高水準となる。サービス化に続く情報化の潮流が、かつての工業化の潮流のように、労働生産性の押し上げ要因になるということだ。また需要創出の面でも、音楽や映像、ゲームなどの情報コンテンツの分野は、消費者のニーズが基礎的な領域から機能の領域、さらには「心」の領域へと高度化してきているなかで、最も有望な分野の一つと位置付けられている(消費者ニーズの高度化については、07年4月付けレポート「消費の行方−市場は「心」の領域へ−」参照)。 資本集約型から知識集約型へ、あるいは、サービス化から情報化へという産業構造の変化の方向転換については、すでにさまざまな視点から議論されてきているが、それらの方向転換は、ここまで見てきたように、生産性向上と需要創出というマクロ経済上の二大要件に対応する動きでもある。それらの新しい潮流においては、人材の高度化と拡充が不可欠であり、場合によってはそれが制約要因となることも考えられる。また、知識や情報を収益化するビジネスモデルの成熟や、資産としての知識、情報を保全する制度的な枠組みの構築といった課題も想定される。これらの課題をクリアし、産業構造の望ましい変化を実現、加速させていくためには、政策的なサポートも求められるが、政府の産業政策が、かつての工業化、重工業化の時代のような大きな影響力を持つことは考えにくい。知識集約型や情報創造型の産業の発展に向けては、個々の企業の戦略的な展開と、叢生するベンチャー企業やマイクロビジネスのバイタリティが原動力となるだろう。これまで以上に日本企業の活力に期待が集まる局面が訪れている。 関連レポート ■「開国」の再定義−産業と文化のOutflowへの注目− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2011年6月14日アップ) ■2010年代の世界の動きと産業の行方 (三井物産戦略研究所WEBレポート 2011年3月18日アップ) ■円高と「通貨戦争」の現実 (三井物産戦略研究所WEBレポート 2010年12月15日アップ) ■日本の存在感−アイデンティティの再構築に向けて− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2010年10月12日アップ) ■日本経済の「今」 (読売isペリジー 2008年10月発行号掲載) ■本当に、日本の労働生産性は低いのか? (チェーンストアエイジ 2008年9月15日号掲載) ■日本産業の方向性−集中と拡散がうながす経済の活性化− (The World Compass 2008年2月号掲載) ■為替レートをいかに考えるか (ダイヤモンド・ホームセンター 2008年2-3月号掲載) ■「成熟期」を迎えた日本経済 (セールスノート 2007年6月号掲載) ■消費の行方−市場は「心」の領域へ− (ダイヤモンド・ホームセンター 2007年4-5月号掲載) ■日本経済「成熟期」の迎え方−新局面で求められる「常識」の転換− (読売ADリポートojo 2006年4月号掲載) ■「豊かさ」と「活力」と−成熟化経済と人口大国の行方− (The World Compass 2006年2月号掲載) ■人口動態と産業構造 (The World Compass 2005年7-8月号掲載) ■歴史から見る次世代産業−第四次産業としての「創造産業」− (読売ADリポートojo2005年7-8月号掲載) ■三つの競争力−脱・デフレを目指す事業戦略のために− (日経BP社webサイト“Realtime Retail”連載 2005年6月16日公開) ■再浮上した成熟化の問題 (The World Compass 2005年4月号掲載) ■経済の活力をどう確保するか−世界に広がる「貧困エンジン」のメカニズム− (読売ADリポートojo2003年12月号掲載) ■競争力を考える−三つの力と日本の課題− (読売ADリポートojo 2002年3月号掲載) ■高齢化時代の日本経済 (The World Compass 2001年5月号掲載) |
||||||||
| Works総リスト |