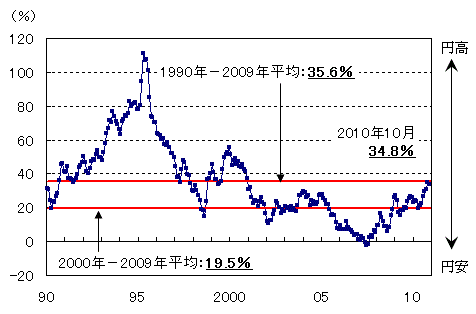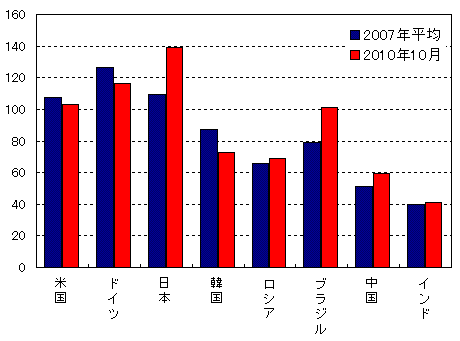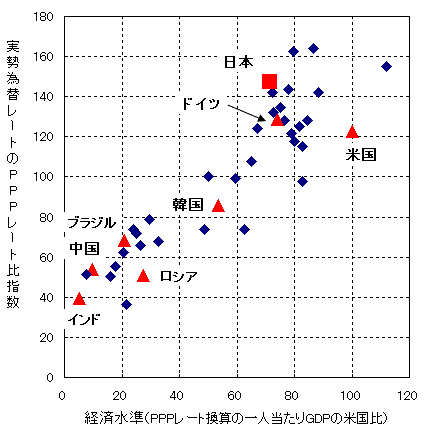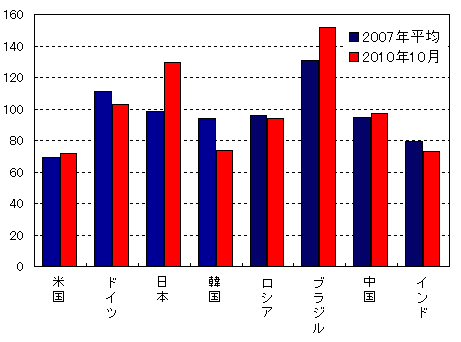| 三井物産戦略研究所WEBレポート 2010年12月15日アップ |
| 円高と「通貨戦争」の現実 |
|
2008年終盤からの世界経済危機を経て、世界各国通貨の為替レートは大幅に書き換えられた。その過程では、自国通貨の引き下げを政策的に進めようという動きが広がり、「通貨戦争」という言葉も生まれた。ここでは、そうした近年の為替レートの動向について考えてみたい。 1ドル80円台のレートをどう見るか まず、日本円の動きから見てみよう。日本円は、2007年半ばまでは、景気の停滞と低金利を理由に大きく下落していた。しかし、サブプライム問題の顕在化を契機に、日本の金融システムが安定していると評価されたことで、円は他通貨に対して大幅に切り上がっていった。2010年10月には、対ドルレートの月中平均で1ドル81.9円と、1995年4月の同83.7円を上回る過去最高値を記録するまでに至っている。 ただ、物価の変動を勘案すると、1995年と2010年では、同じ80円台前半の円ドルレートといっても、その意味合いはまったく異なっている。図表1は、為替レートの一種の理論値とも言えるPPPレート(Purchasing Power Parity=購買力平価、日米それぞれの物価水準から円とドルの購買力が等しくなると想定されるレート)から、市場で実際に取引された実勢の円ドルレートがどれだけ乖離していたかを示したものである。1995年と2010年とは、実勢レートでは同水準であるが、PPPレートからの乖離率を見ると、1995年4月にはPPPレートの2倍(円ドルレートでいえば2分の1)を超える円高であったのに対して、2010年10月は35%程度の円高に過ぎない。
また、経常黒字国である日本の円は、赤字国である米国のドルに比べて割高であることが常態となっており、近時の乖離率の水準は、2007年前後の円安局面を含む2000年から2009年までの平均値19.5%よりは高いが、1990年からの平均値35.6%とはほぼ同水準であり、極端に円高が進んだ状態とは言い難い。 とはいえ、急激な円高は、輸出や企業収益を減退させることに加えて、雇用や設備投資に対する企業のマインドを冷え込ませることにもつながる。今回の円高についても、2007年頃の異例ともいえる円安水準からの急激な反転であることと、それが世界的な経済危機によって需要が大幅に後退するなかで生じたことを考え合わせると、日本の経済、企業にとって、きわめて厳しい事態であることは間違いないだろう。 為替相場変動による明と暗 次に、各国通貨との比較で円の現状を見てみよう。図表2は、世界の主要国のうち、近時の為替動向に関連して特徴的な動きを示している8カ国を対象に、2007年通年と2010年10月の2時点で、それぞれの通貨の実勢レートがPPPレートに対してどれだけ割高・割安になっているかを、主要39カ国の平均を100とした指数で表したものである。この図からは、いずれの時点でも米国やドイツ、日本の通貨が割高になっている一方で、新興国の通貨が割安に評価されていることが読み取れる。市場介入によって人民元のレートを抑えていることを批判されている中国は、主要国の平均に対して、2007年には約5割、切り上げを進めてきた2010年10月にも約4割、割安になっている。
しかし、為替市場において通貨が割安になるのは、中国に限らず、経済が未成熟な新興国全般の傾向と言える(図表3)。その理由としては、各種制度が未整備なことや政治的にも経済的にも不安定であることなどの構造的な要因が考えられる。また、新興国の通貨が割安になっているのは、貧しい国々が輸出によって経済を発展させ貧困から抜け出すことを可能にするためのハンディキャップととらえることもできる。そうした視点に立つと、為替レートの割高・割安は、各国の物価水準だけでなく、経済水準をも勘案して判断する必要があると考えられる。
図表4は、そうした観点から、図表2で示した各国の為替レートの指数について、経済水準の格差に起因する差異を一人当たりGDP(PPPレート換算)の値を用いて調整した各国通貨の実勢水準を表したものである。この図表によると日本は、2007年にはブラジルとドイツを下回り、韓国やロシア、中国とほぼ同水準にあったが、2010年10月にはドイツを抜いて、韓国やロシア、中国を大幅に上回る状態となっている。その背景としては、金融システムの安定性が評価されたことに加えて、この間の各国の金利水準の変化があったものと考えられる。2007年から2010年にかけては、各国が経済危機への対応で金利を大幅に引き下げるなか、日本では2007年の時点で既に極端な低金利の状態にあり利下げ余地がほとんどなかったため、各国との金利差が大幅に縮小し、それがこの間の円高の大きな要因になったものと考えられる。
こうした日本の状況を他国との比較で見ると、通貨安が景気を押し上げているとされる韓国、ドイツとの対照が浮き彫りになる。危機からの立ち直りの早さと、国際市場における企業の躍進が目立つ韓国のウォンは、2007年には日本円とほぼ同水準であったが、金融システムの脆弱性が懸念されたことで実勢レートが大幅に下落し、2010年には日本との格差は2倍近くにまで開いている。また、欧州の輸出大国であるドイツにとってのユーロは、2007年には日本に比べて1割ほど高かったが、2010年には逆に2割以上も割安になっている。これらの結果、韓国、ドイツの輸出競争力は大幅に改善し、経済の回復に大きく効いてきている。 また、先進国では突出した経常赤字国である米国のドルが割安になっている状況は1990年代から変わっていない。一方、為替操作を批判されている中国の人民元は、図表2では、2010年10月時点で、主要39カ国平均比で4割ほど割安になっているが、経済水準で調整した図表4で見ると、ほぼ平均並みで、批判の急先鋒である米国よりはむしろ割高になっている。世界第2位の経済大国となり、巨額の経常黒字を誇る中国を、他の新興国と同列に評価できるかという問題はあるが、現行の人民元の水準にも、一定の合理性があるとは言えるだろう。 「通貨戦争」と円の行方 世界の為替相場が大きく変動し、自国通貨の下落が回復を後押しする構図が鮮明になるなか、通貨安を志向する政策が次第に目立つようになってきた。回復のペースが上がらない先進諸国では、需要刺激を目的とする金融緩和策が通貨安の要因ともなり、いわば一石二鳥の効果を挙げることが注目された。しかし、先進諸国の金融緩和は、先進国から成長力が強く相対的に高金利な新興国への資金の流れを拡大させ、新興国においては、通貨高による輸出の減退や、資金流入の拡大にともなう資産価格の高騰といった弊害が生じることになった。デフレ下で政策金利がゼロ近傍に張り付いているために金融緩和策を取り難い日本が円高に苦しんでいるのも、一部の新興国と同様の状況と言える。資金流入や通貨高に見舞われた国々は、国外からの投資資金への課税強化などによる資金流入規制の強化や市場介入といった手段で対抗しはじめた。こうした状況を「通貨戦争」と呼んで批判の声を上げたのは、図表4において通貨高が最も顕著であったブラジルのマンテガ財務相であった。この議論は11月に米国のFRBが6,000億ドルの国債購入という大規模な金融緩和策を打ち出したことで拍車がかかり、米国に批判が集まった。11月のソウルG20サミットでは、競争的な通貨引き下げ策の抑制という合意は得られたものの、国内経済を対象としてきた金融政策の国外への影響をどのように位置付け、金融政策の国際協調を図っていくかという根本的な問題への答えは見いだせてはいない。 また、このG20サミットを契機に円高の進行は、ひとまず収まる形となったが、アイルランドの財政不安の拡大で欧州の財政・金融危機の再燃が懸念されるなど、世界の金融システムに不安が残っている状況で、金融システムの安定性が評価されている日本の円に上昇圧力が働きやすい構図に変わりはない。今後、円が下落に向かう要因としては、欧州をはじめとする世界の金融システムの不安定要素が解消すること、あるいは米国や欧州の経済が雇用も含めて本格的に回復し金利が上昇すること、といった材料が考えられるが、いずれも2、3年といった短期間では実現されそうもない。国内の要因で円安に向かうことがあるとしても、国内需要の一段の低迷や、財政の悪化、日本企業の競争力低下にともなう貿易収支の赤字化、金融システムの不安定化といった、望ましくないシナリオしか浮かんでこない。 そう考えると、現実的な対応は、1ドル80円台の現行の水準を、動かせない現実と受け止め、そのデメリットを抑制しメリットの享受を図っていくという方向性になる。具体的には、企業活動の海外展開の加速による企業収益の拡大と安定化、新たな輸出産業の創出、国民生活の向上の追求による内需振興といった方向性だ。円高という外圧の力を借りて、これらの構造改革を進めていけるかどうかで、日本の行方は大きく変わっていくだろう。 関連レポート ■「開国」の再定義−産業と文化のOutflowへの注目− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2011年6月14日アップ) ■震災と向き合って−「復興後」をめぐる論点整理− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2011年4月15日アップ) ■2011年の世界経済展望−回復下で鮮明になったリスクと緊張− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2010年12月13日アップ) ■世界経済と為替市場に振り回される日本経済 (ビジネス・サポート 2009年5月号掲載) ■労働生産性から見る日本産業の現状 (The World Compass 2008年7-8月号掲載) ■為替レートと購買力平価 (The World Compass 2008年7-8月号掲載) ■激動期を迎えた為替市場 (投資経済 2008年5月号掲載) ■為替レートをいかに考えるか (ダイヤモンド・ホームセンター 2008年2-3月号掲載) ■ブランドとしての通貨−メジャーの不安とローカルの胎動− (読売ADリポートojo 2005年3月号掲載) ■為替市場介入35兆円−景気維持のための最後の手段− (読売ADリポートojo 2004年5月号掲載) |
||||||||||||||
| Works総リスト |