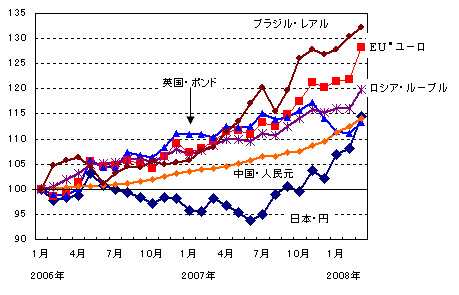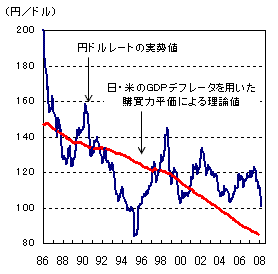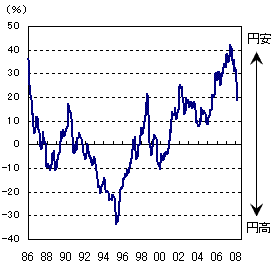| 投資経済 2008年5月号(4月上旬発行)掲載 |
| 激動期を迎えた為替市場 |
|
2007年後半からのドル安の流れは2008年に入ってさらに加速し、3月には約12年半ぶりに1ドル100円の水準を割り込んだ。この動きは、日本経済にも世界経済にも大きな影響を及ぼすものと考えられる。ここでは、現下の為替市場の変動の背景と影響を整理するとともに、今後の市場と経済の展開を考えてみたい。 加速したドル安 多くの通貨に対するドル安の流れは、米国の経常赤字の膨張を背景として、2006年初頭から進んできていた(図1)。懸念されていたパニック的な暴落ではなく、着実ではあるが緩やかな動きであったのは、米国経済が堅調を維持していたことがドルの支援材料となっていたためだと考えられる。
しかし、07年夏に状況は変わった。サブプライム問題の顕在化である。サブプライムローンの不良債権化の影響は住宅ローン市場の混乱にとどまらず、米国を中心とする短期金融市場の多くの部分が機能不全に陥るとともに、欧米の金融機関の多くが巨額の損失を計上したことで、金融システムと米国経済に対する不安感が高まった。08年に入ってからは雇用者数が減少に転じるなど、米国の実体経済への悪影響も鮮明になってきている。その結果、「堅調な米国経済」という歯止めがはずれ、ドル安の流れが加速したのである。世界的な株安や、金融商品との対比で買い圧力が高まった原油をはじめとする国際商品市場の高騰も、同じ文脈だ。 そうした流れのなか、円の動きに注目してみると、07年夏までの期間は、大半の主要通貨に対してドルが下落するなかで、円はそのドルに対してさえ下落していた。いわば「円安・ドル安」の状況だったわけだ。その背景としては、デフレという言葉に象徴される経済の活力の低下と、それを反映した超低金利状態のために、国内投資家が円を売って外貨で運用する動きや、各種のファンドが円で資金を借りてそれを他の通貨に換えて運用する、いわゆる円キャリー取引が広まったことが挙げられる。こうした動きが07年夏以降は停止あるいは反転した。その結果、円はドルに対して上昇に転じ、ドル以外でも一部の通貨に対しては、それまでの下落分を取り戻す形で上昇してきている(前掲図1)。 日本経済への影響はプラスとマイナスの双方向 日本では円高というと、景気への悪影響という想像が働きやすい。確かに、輸出に際しては収益性や競争力が低下するし、海外での事業収益が円換算の際に目減りすることが企業収益に及ぼすマイナスの影響も、近年では大きくなってきている。そのインパクトは、ドル以外の通貨に対しては対ドルほどの円高にはなっていないため限定的だと考えられるが、経済の活力を低下させている現在の日本にとって、決して無視できるファクターではない。 しかし、円高にはメリットもある。一つは、輸入価格の低下にともなうコストダウン効果である。原油や農産物の価格が上昇している状況でもあり、円高にともなう輸入価格の低下は、企業収益にも個人消費にもプラスの影響を及ぼすものと考えられる。 こうしたメリットとデメリットを合わせて勘案すると、おおまかに言って、輸出も含めて国外の市場を対象とする事業展開を進めてきた自動車や電気機械、建設機械など日本の中核産業の大手企業にはデメリットが大きいのに対して、国内での展開にとどまりコスト上昇分の転嫁もままならない中小企業にメリットが及ぶということになりそうだ。 また世界経済全体の視点からすると、もう一つ重要な影響として、むしろドル安のメリットと言うべきではあるが、米国の景気を下支えする効果が期待できる。円高下の日本の場合と逆に、ドル安下の米国では、米国製品の国際競争力の向上や、米国企業が欧州や日本で稼ぐ収益がドル換算で膨らむことが企業収益を改善させるものと考えられる。 米国経済の失速は、世界経済全体の停滞につながる。中国をはじめとする新興国は高成長を続けているものの、米国向けの輸出が落ち込む影響は小さくはないはずだ。欧州や日本も、自律的な成長軌道に戻ってきてはいるが、やはり米国の失速の影響は大きいだろう。現下のドル安は世界経済全体の安定に貢献することを通して、日本にも恩恵が及ぶことになる。中長期的には、この面からのメリットが最も重要だと考えられる。 近年の為替相場の動きは、2007年前半まではデフレを抜け出せない日本経済に対して、また07円後半からはサブプライム問題を抱える米国に対して、それぞれ円安、ドル安という国際的なサポート、あるいはハンデキャップが与えられていたのだという見方もできる。それは、現在の為替市場に、各国の経済の総合的な状況を評価するような、ある種のバランス感覚が存在しているということでもある。 相場観が支配する世界 近年の為替市場が、ある種のバランス感覚に沿って動いている背景には、取引に参加する多くのプレーヤーがそれぞれに売ったり買ったりを繰り返すことで、貿易などによる実需をはるかに超える巨額の取引が成立していることがある。そのため、市場での価格形成は、実需に機械的に縛られることはなくなり、個々の市場参加者の相場観を集約する形で行われている。近年の為替市場の変動が日本の超低金利や米国の経常赤字、サブプライム問題を背景にしていると言っても、それらが直接的にドルや円の需給関係を動かしたわけではない。それらの事象が市場参加者の相場観を変化させることで、ドル安や円安の圧力が生じ、相場を動かしているのである。それは為替市場だけでなく、株や債券、国際商品など多くの市場に共通する構図でもある。 為替市場の参加者の相場観を変化させるファクターは、各国の経常収支や金利だけでなく、景気や物価、各種の政策、政治や社会の安定性など、きわめて多岐に及ぶうえ、それらのうちどれが重視されるかは状況によって変化していく。その変化を踏まえて為替レートの動きを予想することはきわめて難しい。ただ、敢えて簡潔に整理してみると、近時の為替レートの決定要因は、その通貨が流通している経済の「活力」と「健全性」という二つの尺度にまとめることができそうだ。経済活動が活発で成長力の高い国の通貨には上昇圧力が働く。しかし、たとえ「活力」のある経済であっても、財政赤字や経常赤字の拡大、過度のインフレ、あるいは金融システムの動揺といった経済の「健全性」を損なうような動きがあれば、その国の通貨には下落圧力が働いてくる。 サブプライム問題が顕在化してからのドル安は、まさにその典型と言えるだろう。ドルに関しては基軸通貨としての信任を問う議論も出てきているが、これについても、ユーロの台頭という趨勢はあるものの、現時点では、米国の経済と金融システムの健全性への懸念の一環と位置付けられる。 ドルの行方、円の行方 こうした前提のうえで、今後の為替市場の展開を考えてみると、当面はサブプライム問題の動向が最大のカギであることは言うまでもないだろう。問題の緩和に向けた道筋が見えてくればドル安の圧力は低下し、ドル高への修正がはじまることが想定されるが、それまでの間は、ドル安方向への圧力が働き続けるものと考えられる。 ただ、サブプライム問題が解消に向かわず、米国の実体経済がさらに悪化するような展開になると、その影響は欧州や日本、さらには新興諸国にも及ぶため、一方的なドル安が続くとは限らなくなってくる。為替レートは、あくまでもそれが流通している国・地域の活力と健全性の相対的な位置付けによって決まる傾向にあるからだ。すでに米国の実体経済は景気後退に入ったとの見方が強まるほどに悪化している。次の段階では、サブプライム問題の展開に加えて、米国の実体経済の悪化の動向と、それが世界各国・地域の経済にどれだけの影響を及ぼすかにも注意が必要になる。為替市場の展開は複雑さを増し、場合によっては、それぞれの通貨がドルに対して急騰、急落を繰り返す展開になる可能性もある。 一方、円の行方を考えてみると、当面はドルおよび米国経済との相対関係に左右される展開が想定されるが、その先では「脱デフレ」が最大のカギとなるだろう。日本経済が明確にデフレの状況を抜け出せれば、健全性の回復という意味合いから、円には上昇圧力が働いてくることが予想される。 円の行方を予想するうえでのもう一つのポイントが、「購買力平価」の考え方である。購買力平価とは、各通貨と物財との関係、すなわち物価を媒介にして、通貨間の相対価格である為替レートの理論値を算出しようという考え方である。そこでは、物価の上昇は物財に対する通貨の価値の下落を意味するため、その通貨は他通貨に対しても減価するはずだという前提が置かれ、インフレ率が高い国の通貨は低い国の通貨に対して、その差の分だけ減価することが想定される。よく引き合いに出される「ビッグマック指数」や、物価上昇分を除いた為替レートの動向を示す「実質レート(実質実効レートも含む)」を用いた議論も、購買力平価の考え方を下敷きにしたものである。 それらも含めて、購買力平価の考え方は、従来の為替市場では基本的な物差しとして認識されていた。ところが近年の円の動きは、それから大きく逸脱したものであった。購買力平価の前提に立てば、物価が下落するデフレの現象は通貨価値の向上を意味し、理論的には他通貨に対して上昇することが想定される。しかし現実には、2005年頃からの円安局面においては、デフレとそれを背景にした超低金利が円安材料と判断され、図2、3に見られるように、円・ドルのレートは購買力平価の考え方で算出される理論値から大幅に円安方向に乖離した状態が続いていた。円に関しては、購買力平価の考え方は完全に放棄されていたのである。
ところがここにきて、ドルに対する円高が急速に進んだことで、相場観の修正の拠り所という位置付けで、いったんは放棄されていた購買力平価の考え方が再認識される可能性が生じてきた。購買力平価の考え方で算出される理論値は、参照する物価指標や対象とする期間の据え方によって相当な幅があるが、2008年3月の1ドル100円近傍という水準よりもさらに大幅に円高に振れた水準がターゲットとして認識されることも十分考えられる(図2の例では、直近の理論値は1ドル85円台)。その一方で、日本の超低金利という円安圧力も依然として残っている。 いずれにしても、それらを織り込んで相場を動かすのは市場のプレーヤーの相場観の動きであり、経済のファンダメンタルズを見ているだけでは予想がつかない。まさに「相場のことは相場に聞け」という格言どおりの状況だ。サブプライム問題を背景とした円高は、市場のプレーヤー同士が相場の動きを通じて相互にそれぞれに相場観を確かめ合う、きわめて不安定な激動の局面のはじまりを意味しているのかもしれない。 関連レポート ■円高と「通貨戦争」の現実 (三井物産戦略研究所WEBレポート 2010年12月15日アップ) ■世界経済と為替市場に振り回される日本経済 (ビジネス・サポート 2009年5月号掲載) ■日本経済回復のシナリオ−「タダ乗り」への期待と懸念− (The World Compass 2009年3月号掲載) ■世界の激動が店頭を変える (チェーンストアエイジ 2008年12月15日号掲載) ■本当に、日本の労働生産性は低いのか? (チェーンストアエイジ 2008年9月15日号掲載) ■労働生産性から見る日本産業の現状 (The World Compass 2008年7-8月号掲載) ■為替レートと購買力平価 (The World Compass 2008年7-8月号掲載) ■米国経済に潜むトリプル・スパイラルの罠 (投資経済 2008年7月号掲載) ■為替レートをいかに考えるか (ダイヤモンド・ホームセンター 2008年2-3月号掲載) ■2008年の世界経済展望−新たな秩序形成が視野に− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2007年12月14日アップ) ■経済の安定と市場の不安定 (三井物産戦略研究所WEBレポート 2007年8月7日アップ) ■ブランドとしての通貨−メジャーの不安とローカルの胎動− (読売ADリポートojo 2005年3月号掲載) ■為替市場介入35兆円−景気維持のための最後の手段− (読売ADリポートojo 2004年5月号掲載) ■読めない株式市場−現代経済のアキレス腱− (読売ADリポートojo2001年3月号掲載) |
|||||||||||
| Works総リスト |