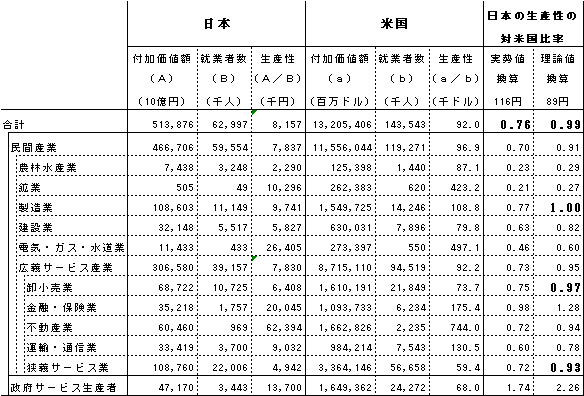| チェーンストアエイジ 2008年9月15日号掲載 |
| 「データで見る流通」 本当に、日本の労働生産性は低いのか? |
|
日本の産業は、卸小売業を含むサービス産業を中心に、欧米諸国に比べて労働生産性が低いと言われることが多い。実際、日米の2006年のGDP統計から両国の労働生産性を計算してみると、下表のとおり、同年中の平均為替レート(1ドル=116円)でドル換算した日本の労働生産性は、対米国比で0.76倍と、米国を大幅に下回る水準になっている。ただ、同様の計算を2000年のデータで行ってみると、日本の労働生産性の対米国比は1.06倍と、日本が米国を上回っていたという結果が得られる。 この結果をそのまま受け止めると、2000年から2006年までの間に、日米のいずれか、あるいは双方で生産効率の大幅な変動があったように見える。しかし実際には、そのような大きな変化が生じたとは考え難い。そうなると、両国の物価上昇率の差と為替レートの変動が影響している可能性が想起される。そこで、両国の物価上昇率の差と為替レートの変動の影響を取り除くため、購買力平価の考え方で求めた各年の為替レートの理論値(2006年時点で1ドル=89円)を用いて換算し直してみると、日本の労働生産性の対米国比は1998年から2006年まで、1.01倍から0.99倍の間で安定的に推移しているという結果が得られる。 この結果から見ると、この間の日米両国の実質的な労働生産性はほぼ等しい状況が続いていたという結論になる。言い換えると、2006年の日米の労働生産性に大きな差が生じているのは、日本の超低金利を背景とする極端な円安によるものであり、労働生産性の低下という表現から思い浮かぶような、生産活動の効率の大幅な低下が生じているわけではないということだ。 次に、日本の産業別の労働生産性を見ると、卸小売業と狭義サービス業は、全産業平均を100とした指数で、それぞれ78.6、60.6と、いずれも大幅に低い値となっている。ただ、これも対米国比の値で見てみると、製造業の1.00倍(円・ドルの換算に理論値を使用したベース)に対して、卸小売業が0.97倍、狭義のサービス業が0.93倍と若干低いものの、その差は極端に大きなものとはなっていない。そこから考えると、労働生産性の業種間の格差は、いわゆる労働集約的な産業か資本集約的な産業かの違い、すなわち、それぞれの生産活動における人手による労働から資本設備の利用への置き換えの容易さを反映したものと言えそうだ。 こうしたデータから見て、為替レートの変動の影響を取り除けば、日本の労働生産性は米国に対して、必ずしも大きく劣後しているわけではなさそうだ。卸小売業に限ってみても同じことが言える。このことは、日本や米国、欧州のような先進国の成熟した市場においては、経済発展や企業間競争に向けた焦点は、既に、生産活動の効率性という意味での生産性から、新たな市場の開拓や、商品・サービスの高付加価値化に必要な「創造性」へ移行していることの証左の一つと言えるのではないだろうか。 |
||||
関連レポート ■日本経済の「今」 (読売isペリジー 2008年10月発行号掲載) ■労働生産性から見る日本産業の現状 (The World Compass 2008年7-8月号掲載) ■激動期を迎えた為替市場 (投資経済 2008年5月号掲載) ■為替レートをいかに考えるか (ダイヤモンド・ホームセンター 2008年2-3月号掲載) ■消費の行方−市場は「心」の領域へ− (ダイヤモンド・ホームセンター 2007年4-5月号掲載) ■三つの競争力−脱・デフレを目指す事業戦略のために− (日経BP社webサイト“Realtime Retail”連載 2005年6月16日公開) ■リテールビジネスは創造力の時代へ (日経MJ 2004年12月6日付第2部「新卒就職応援特集」掲載) ■消費者を動かす力−脱・安売り競争時代のキーワード− (チェーンストアエイジ 2004年10月1日号掲載) ■競争力を考える−三つの力と日本の課題− (読売ADリポートojo 2002年3月号掲載) |
||||
| Works総リスト |