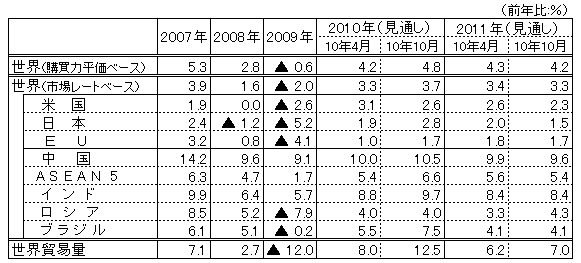| 三井物産戦略研究所WEBレポート 2010年12月13日アップ |
| 2011年の世界経済展望−回復下で鮮明になったリスクと緊張− |
|
回復局面での新展開 2010年の世界経済は、ペースの変動はあったものの、均してみれば、前年から引き継いで、緩やかな回復基調を維持したと言える。2009年に大幅に落ち込んだ世界の貿易総額も2010年にはほぼ危機前の水準に回復している。また原油価格も、経済の回復を先取りする形で上昇し、2009年の終盤以降は概ねWTIで 1バレル80ドル前後の推移となっている。そうしたなか、回復局面での新たな展開も生じている。 第一に、米、欧、日の先進諸国において、経済政策の最重要テーマが変質したことが挙げられる。先進諸国では、プラス成長を続けてはいるものの失業率は高止まったままの状態にある。さらに5月の欧州諸国の財政・金融危機の高まりを受け、財政への目配りも必要になった。危機自体は、危機下の国に対する国際的な支援体制が構築されたことでひとまず落ち着いたが、その影響で、先進国の経済政策の中心課題は、非常時の体制から平時の体制への移行のタイミングを図る「出口戦略」ではなくなり、「景気刺激と財政再建の両立」というより困難なものへと変質したのである。 第二には、先進国と新興国の間で、景気の局面が大きく乖離してしまったことが上げられる。新興国の多くは、先進国とは対照的に、順調に回復軌道を進んできた。その結果、新興国主導の世界経済という構造転換が一段と鮮明になったが、それと同時に、多くの新興国で、インフレ懸念が高まったり、資産価格が高騰しバブルの懸念が生じたりといった形で、景気の過熱に対する配慮が必要になってきた。そうした国々では、既に金融を引き締める動きが広がってきつつあり、世界全体が回復に向けた景気刺激策を展開していた2009年の状況からは様変わりと言える。
「通貨戦争」の発生 2010年には、先進国における経済政策の変質と、先進国と新興国の景気局面の乖離が重なったことで、先進国と新興国の間で、経済政策をめぐる緊張が高まった。景気刺激と財政再建の両立を迫られた先進諸国では、需要刺激を目的とする金融緩和が一段と強化されたが、それは自国通貨の下落を通じて輸出を後押しする形となり、いわば一石二鳥の効果を挙げた。しかし、その裏側では、多くの新興国がネガティブな影響を被ることになった。新興国のなかでも回復の途上にある国々にとっては自国通貨高による輸出抑制が回復の阻害要因となった。他方、既に回復が進んでインフレや資産バブルの懸念が生じている国々にとっては国外からの資金流入を加速させインフレや資産バブルの懸念を一段と強めることになった。 そうした事態を受け、多くの新興国が、自国通貨の引き下げを狙った市場介入や、課税等による国外からの資金流入に対する規制強化といった対抗策を講じるとともに、先進国の金融緩和策に対する批判を強めていった。9月末には、通貨レアルの上昇に悩むブラジルのマンテガ財務相がこうした状況を「通貨戦争(Currency War)」と呼んで非難したことで、この問題に対する認識が広く共有されることになった。形を変えた保護主義の動きとも言えるこの問題は、11月にソウルで開催されたG20サミットの主要議題となり、競争的な通貨引き下げ策の抑制という合意には達したものの、国内経済を対象としてきた金融政策の国外への影響をどのように位置付け、金融政策の国際協調を図っていくかという根本的な問題への答えは見出せてはいない。 国際的な政策協調の進展は不十分 2010年前半に世界的な問題となった先進国の財政不安と、年後半に議論が高まった「通貨戦争」の問題は、それぞれ、7月のG20トロント・サミットと、11月のソウル・サミットで主要議題となった。G20サミットでは、いずれの問題に対しても、国際的な政策協調を図っていくことが合意された。 G20の首脳会合は、世界金融危機への対応策を講じる目的で、2008年11月にワシントン、2009年4月にロンドン、9月にピッツバーグで随時開催されたが、ピッツバーグでは、G20サミットを「国際経済協力に関する第一のフォーラム(premier forum)」と位置付け、危機対応だけでなく、気候変動問題や国際的な産業規制、通商問題を幅広く扱う場として定期開催することが合意された。しかし、2010年のトロントとソウルでのサミットは、財政不安と為替問題という喫緊の課題への対応に終始し、定期開催化した目的を十分に達したとは言い難い結果となった。 G20サミットについては、経済水準や体制を異にする20もの国でコンセンサスを形成することは難しいとの懸念もあった。2010年のサミットでは、危機対応に追われたこともあって、その懸念が現実のものとなった感が強い。しかし、中国をはじめとする新興国の存在感が急速に拡大するなか、主要な先進国と新興国が揃って政策協調を図る枠組みとしての必要性は明らかであり、2011年以降は、段階的に合意形成の場としての機能を高めていくことが期待される。 2011年もリスクファクターを抱えながら緩やかな回復基調を維持 以上の流れは、2011年にも引き継がれることになる。世界経済については、引き続きペースの緩やかな構造転換型の回復を維持することがメインシナリオと想定される。回復の原動力となる構造転換としては、先進国から新興国への成長の主役交代に加えて、産業構造においても、新たな主役の台頭が期待される。2010年の段階で既に、先進国の政府と企業が連携したパッケージ型輸出やシステム輸出のスタイルで、新興国におけるインフラ需要の取り込みを競う動きが本格化している。それに続いて、「資源・環境」「医療・健康」「安全・安心」といったニーズの存在が明確な領域で、新たな産業が形成されていく展開にも、引き続き期待がかかる。 一方、リスクファクターについても、2010年に顕在化したものはいずれも解消されないまま、2011年に持ち越されている。欧州の財政・金融不安は国際的な支援体制は構築されたものの、年終盤になってアイルランドで懸念が高まったように、各国の財政赤字の問題自体は依然残されている。日、米も含めた先進国の大半が、経済政策において景気維持と財政再建の両立という難しい舵取りを迫られている状況も変わっていない。「通貨戦争」が再燃する可能性もある。 これらの問題に対応するための政策手法は2010年の段階で既に確立されており、世界経済が危機的な状況に陥る可能性は大きくはない。ただ、そうした政策が的確に実行されるかという点で、中間選挙で敗北したオバマ政権の米国や、政権交代後の混乱をいまだに抜け出せずにいる日本など、主要国の一部で、政権が求心力を低下させていることが懸念材料となる。欧州でも、2010年4月に選挙を控えたドイツがギリシャ支援策への支持を渋り危機を深刻化させたのと同様の形で、政治リスクが顕在化する可能性は否定できない。中国においても、政権と軍や党内の対外強硬路線、既得権者との間で一部意見の対立が指摘されており、今後の政策展開には不安が残る。 加えて、政権の求心力の低下は、各国の対外的な強行姿勢につながりやすく、国際協調の進展にはネガティブな要素となるし、環境や医療、安全の領域での新産業の形成に向けても、そのために不可欠な公的な助成や規制改革、制度の再設計を停滞させるという意味で、大きな阻害要因となる。各国の政治動向は、引き続き、経済や産業の展開を見通すうえでも、最重要ファクターと位置付けられる。 関連レポート ■2011年後半の世界経済展望−回復の持続と高まるインフレ懸念− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2011年6月10日アップ) ■2010年代の世界の動きと産業の行方 (三井物産戦略研究所WEBレポート 2011年3月18日アップ) ■円高と「通貨戦争」の現実 (三井物産戦略研究所WEBレポート 2010年12月15日アップ) ■2010年後半の世界政治・経済−回復する経済と高まる政治リスク− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2010年6月11日アップ) ■2010年の世界経済地図 (読売isペリジー 2010年4月発行号掲載) ■2010年の世界経済−危機脱却から構造転換へ− (環境文明21会報 2010年1月号掲載) ■2010年の世界経済展望−見えてきた金融危機後の世界− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2009年12月10日アップ) ■2009年の世界経済マップ−金融危機のインパクト− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2009年9月10日アップ) ■危機下の世界経済−反動としての「大きな政府」路線と国際協調への期待− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2009年6月15日アップ) ■資本主義はどこへ向かうのか (The World Compass 2009年2月号掲載) ■世界金融危機の行方 (読売isペリジー 2009年1月発行号掲載) ■世界の激動が店頭を変える (チェーンストアエイジ 2008年12月15日号掲載) ■2009年の世界経済展望−危機下で進む新秩序の模索− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2008年12月12日アップ) ■米国株価下落に見る世界金融危機−歴史的転換点を求める局面− (投資経済 2008年12月号掲載) ■米国経済に潜むトリプル・スパイラルの罠 (投資経済 2008年7月号掲載) ■2008年の世界経済展望−新たな秩序形成が視野に− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2007年12月14日アップ) ■世界経済の減速をどう見るか−安定化に向かうなかで漂う不安感− (読売ADリポートojo 2007年6月号掲載) |
|||||
| Works総リスト |