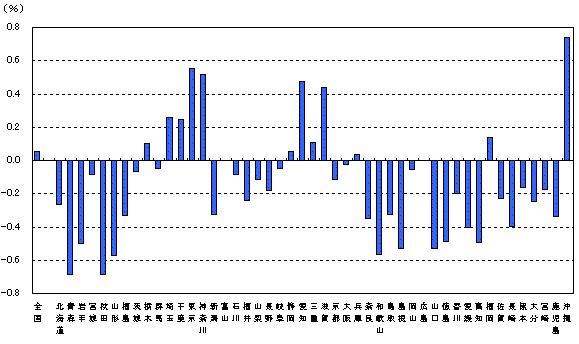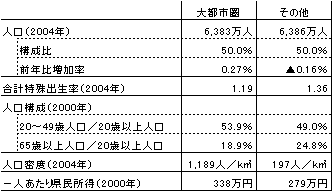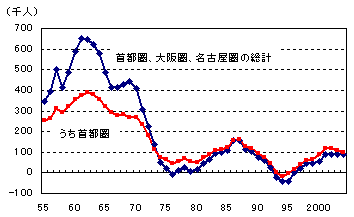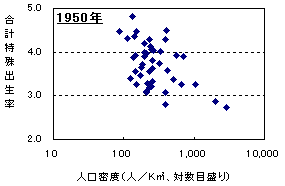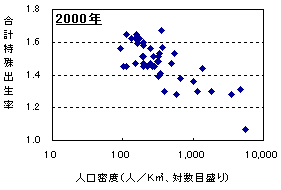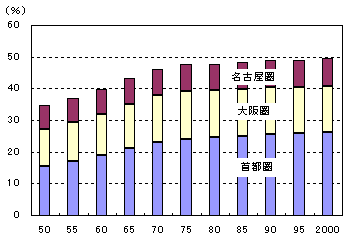| The World Compass(三井物産戦略研究所機関誌) 2005年7-8月号掲載 |
| 人口動態と産業構造 |
|
「人口減少時代」が、いよいよ目前に迫ってきた。従来予想されていたよりも早く、今年、2005年が日本の人口が最も多かった年、あるいは減りはじめた年として記憶されることになりそうだ。 人口の動きは、社会のさまざまな領域の多彩なファクターが絡み合って形作られる。その全体像を把握することは容易ではないが、そこでは、経済や産業の動きも、大きな役割を果たしているものと考えられる。 減少と集中と 2004年には、日本の人口は0.05%とごく小幅ながら増加した。これを都道府県別にみると(図表1)、東北や山陰、四国、九州など多くの県で人口は減少している。地図上で人口が減っている県を塗っていくと、国土の面積の8割以上が塗りつぶされることになる。 しかしその一方で、沖縄、東京、神奈川、愛知、滋賀といったあたりが明確な増勢を維持しているのをはじめ、12の都県では、人口は依然として増え続けている。そして、それらの都県の多くが、人口が集中している地域であるため、日本の総人口のほぼ半数が、人口が増えている都県に居住している形になっている。さらに、減少している県においても、人口の多い都市部では人口増が続いているケースが多い。そのため、個人のレベルでは、自身の生活空間において人口減少を経験している人は、依然として少数にとどまっているのである。
この状況は、日本の人口減少が田舎からはじまっていることを示しているが、人口減少の最大の要因である少子化の進行においては、従来から都会の方が先行している。一人の女性が一生の間に産む子供の数を表す合計特殊出生率をみると、大都市圏(東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知、岐阜、三重、大阪、兵庫、京都、奈良の11都府県)の1.19に対して、その他の道県では1.36となっている(図表2、いずれも各県別の値を人口でウェイト付けして加重平均した値)。これは、少子化の傾向は都会でも田舎でも見られるものの、その程度は都会の方がより甚だしい、あるいは先行しているということだ。
にもかかわらず、田舎の方が先に人口を減らしはじめているのは、田舎から都会への人口移動が続いていることもあるが(図表3)、それに加えて、田舎では子育て世代の人の割合が低いことが大きな要因となっている(図表2の「人口構成」の項目参照)。子育て世代の人々それぞれが生み育てる子供の数は田舎の方が多いが、その世代の人の割合が小さいため、出生数が死亡数と県外流出に追いつかず、人口が減少するという図式である。そして、田舎における人口減少は、都会への人口集中の傾向を、一段と際立たせることにもつながっている。
背景は高度成長期以来の産業構造の変動 都会への人口集中、さらには日本全体の人口が減少に向かいつつある背景には、日本経済が高度成長を遂げた1950年代から60年代にかけて起きた産業構造の変化が大きく影響している。それは、「ペティ=クラークの法則」(関連レポート『歴史から見る次世代産業』参照)で言うところの、第一次産業から第二次産業への移行であった。 1950年代から60年代の日本経済の高度成長においては、欧米先進国からの技術導入に加えて、第二次産業への移行が急速に進んだことの寄与が大きかった。労働生産性と所得水準の高い製造業に資本と人材が振り向けられたことが、経済全体の生産性と所得水準を押し上げたのである。そして、製造業の設備とインフラが都市部に集中して構築されたために、製造業への移行は、必然的に農村から都市部への人口移動をともなう形で進行したのである。 1956年から70年までの15年間の累計で、首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)には476万人、大阪圏(大阪、兵庫、京都、奈良)210万人、名古屋圏(愛知、岐阜、三重)61万人、合計で748万人が大都市圏に流入した(流出者を除いた純流入)。これは、70年時点の日本の総人口の7.1%、大都市圏人口の15.5%にも達する人数であるが、その多くが、新たに職を得ようとする若年層であった。そこにはもちろん、団塊の世代の人々も含まれていた。 この時期に生じた都市部への人口移動は、急速な経済成長を可能にするうえで不可欠な要素の一つであった。裏返せば、それなしでは、日本の高度成長は限定的なものにとどまった可能性が高いということでもある。その一方で、この時期以来の経済の発展が、現在の日本社会の悩みの種である少子化の傾向を加速させた面もある。経済成長の結果、所得水準が向上したことで、お金で買える楽しみが多様化、高度化し、それが若い世代の人々に、子育てに時間とエネルギーを費やすことを躊躇させる一因になったと考えられるためだ。 さらに、この時期の人口移動自体が、少子化の遠因となった可能性もある。人口の集中する都会では、住宅事情の悪さや生活コストの高さもあって、田舎と比べて子供を産む数は従来から少なかった(図表4)。高度成長期の人口移動は、子供を産み育てる年代の人々を、子育てしにくい地域へ導く形になったのである。加えて、新たに移り住んだ都会では、田舎と違って、親や親戚に子育ての支援を期待し難かったことの影響も大きかったものと考えられる。
そうしたことを含め、因果関係は複雑ではあるが、高度成長期の産業構造の変動が、今日まで続く都会への人口集中、さらには、これからはじまる人口減少の要因の一つとなっていることは、ほぼ間違いのないところと言えるだろう。 70年代に入ったところで第一次産業から第二次産業への移行は一段落した。それにともなって高度成長も終焉を迎えた。その後、日本経済はサービス産業を中心とする第三次産業への移行段階に入っていった。しかし、都会への人口移動は、ペースこそ鈍ったものの、依然として続いている。それは、第三次産業の固有の性格によるところも大きい。 自然を相手にする第一次産業が中核であった時代には、仕事の多くは自然環境に固定され、人々は農地や森林、漁場に縛られていた。それが、第二次産業が主力になると、仕事は資本設備に付随して生み出されるようになり、人々は投下される資本に吸い寄せられて都会へと移動した。そして第三次産業においては、人が集まっていること自体が仕事を生むという傾向が強い。さらに、製造業などにおいても、管理部門や販売、開発など、第三次産業的な性格の仕事のウエートが大きくなったこともあって、集中が集中を呼ぶ循環的な構造が生じているのである。 これは、高度成長期の第二次産業への移行によって形成された都会への人口集中の構図が、第三次産業への移行にともなって固定化されたということだ。近年では、大都市圏の人口は全体のほぼ5割にまで上昇している(図表5)。
こうした状況を前提にすると、人口の集中傾向はまだ当分続きそうだと考えざるを得ない。そして、人口集中が少子化の一因であるとすると、人口の減少傾向が緩むことも期待し難い。この状況が変わるとすれば、人々の生活や仕事に対する考え方、あるいは産業構造の変化がカギを握ることになるだろう。 第四次産業が新しい潮流を生む? 生活や仕事に対する考え方という意味では、お金で買える楽しみや便利さを一通り経験したことで、都会では失われた良好な生活環境の価値が見直され、田舎に移り住む人が増えるという動きが生じている。一度は都会に出てきた若者が故郷に帰って仕事を見つける「Uターン」に加えて、故郷以外の田舎へ移る「Jターン」、都会生まれの人が田舎に移り住む「Iターン」といった言葉も、すでに流行語の域を超えて定着している。 例えば沖縄県では、90年代末あたりから、県外からの流入が流出を上回る状態が定着している。2004年、沖縄県の人口は0.74%増加したが(図表1)、そのうち0.21%分は、県外からの流入超によるものだ。流入超過数は、98年から2004年までの累計で1万2千人ほどと、全体の規模からするとまだまだ小さな動きに過ぎないが、これからの人口動態を考えるうえでは、見逃せない動きと言えるだろう。 仕事や雇用をめぐる変化も、こうした動きを加速させる可能性がある。バブル崩壊後の長期不況の末にリストラが常態化したことで、企業と雇用者の関係は大きく変質した。「大企業のホワイトカラー」という、従来型のサクセスモデルの優位性が後退するなかで、若年層を中心に、企業に依存しない、新たな人生設計のモデルを模索する動きが活発化している。それは、必ずしも都会への人口集中を妨げる動きに直結するわけではないが、人々を都会に縛り付ける力を弱めることにはつながるだろう。 また、産業構造や生産活動の面でも、これからの人口動態に影響を及ぼしそうな変化が起きつつある。それは、情報通信環境の飛躍的な高度化によって、業務を行う場所や時間帯をフレキシブルに設定できる状況が生まれてきたことによるものだ。それを受けて、事務処理や顧客からの電話への対応といった定型的な業務を、賃金や地代の安い地域に移管することが、企業にとっての現実的な選択肢となっている。雇用の場が都会から田舎へ流出、分散する可能性が生じているということだ。 さらに、映像や音楽、ソフトウェア、デザイン、商品企画など、情報コンテンツを創造する仕事においても、距離や時間を超えた協業が可能になっている。各種のドキュメンツや画像、音声、プログラムといった情報をネットを使って離れた場所でやり取りしながら、市場価値を備えたコンテンツを完成させていくスタイルだ。マイクロソフトのWindowsに対抗するOSを構築しようという呼びかけに応えて、世界各地の技術者がボランタリーに参画した“LINUX”のプロジェクトもその典型例だ。 情報創造の領域は、これからの経済において、一段とウェイトを高めていくことが予想される。慢性的な供給過剰にあえぐ多くの企業が、新製品の企画やデザインのような創造性を要求される仕事の重要性を改めて認識し、そこに戦力を集中させる傾向が強まっている。デザインや企画だけを専門に行う企業も増えてきた。加えて、消費者のニーズが高度化したことで、人々を楽しませたり感動させる情報コンテンツを創造することの重要性も、一段と高まってきている。 これらの創造的な仕事をするうえでは、生活環境の優れた田舎が良いのか、それとも、生活環境は悪くても何かと刺激の多い都会が向いているのかは一概には言えない。ただ、ここでもやはり、都会に限られていた仕事の場が、その選択肢を広げる可能性があることは確かだろう。 ここで注目した情報創造型の産業群は「情報」の形で価値を残す産業であり、「モノ」の形で価値を残す第二次産業とも、サービスの形で生産した価値をその場で消費して残さない第三次産業とも、本質的に異なっている。そうした概念的な異質性と、これからの時代における発展性を考え合わせると、情報創造型の産業群を、第三次産業に続く「第四次産業」と位置付けることもできそうだ。 中核産業が第二次産業、第三次産業へと移行してきたプロセスでは、日本においては人口の集中傾向と減少傾向が生じた。第四次産業への移行によって、それとは違う新たな潮流が生まれるのか。ここで取上げた動きは、いずれもまだ微かな兆しといった程度のものに過ぎないが、日本の経済、社会の将来像を描き出すうえでは、大きな意味のある動きと言えるだろう。 関連レポート ■震災と向き合って−「復興後」をめぐる論点整理− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2011年4月15日アップ) ■2010年代の世界の動きと産業の行方 (三井物産戦略研究所WEBレポート 2011年3月18日アップ) ■高齢化の何が問題か (読売isペリジー 2010年10月発行号掲載) ■労働生産性から見る日本産業の現状 (The World Compass 2008年7-8月号掲載) ■日本産業の方向性−集中と拡散がうながす経済の活性化− (The World Compass 2008年2月号掲載) ■課題としての巨大都市−重荷となる大都市圏への人口集中− (読売ADリポートojo 2007年9月号掲載) ■価値としての「情報」−成熟時代の豊かさのカギ− (読売ADリポートojo 2007年5月号掲載) ■チャンスとしての「2007年問題」 (ダイヤモンド・ホームセンター 2006年2-3月号) ■歴史から見る次世代産業−第四次産業としての「創造産業」− (読売ADリポートojo2005年7-8月号掲載) ■人口の減少と集中と−高度成長の重いツケ− (読売ADリポートojo 2005年6月号掲載) ■パズルの大枠−「人口動態」と「豊かさ」の行方− (日経BP社webサイト“Realtime Retail”連載 2005年4月15日公開) ■再浮上した成熟化の問題 (The World Compass 2005年4月号掲載) ■一人一人の高齢化問題−「生涯現役社会」へ向かう時代のベクトル− (読売ADリポートojo 2003年9月号掲載) ■高齢化時代の日本経済 (The World Compass 2001年5月号掲載) ■これからの仕事−21世紀、豊かさは仕事から− (読売ADリポートojo2000年12月号掲載) |
|||||||||||||||||
| Works総リスト |