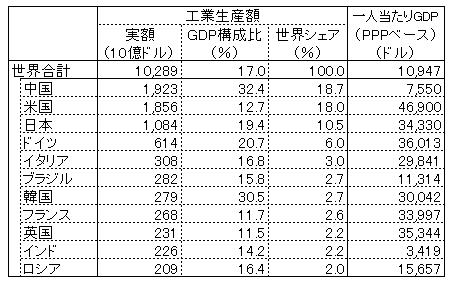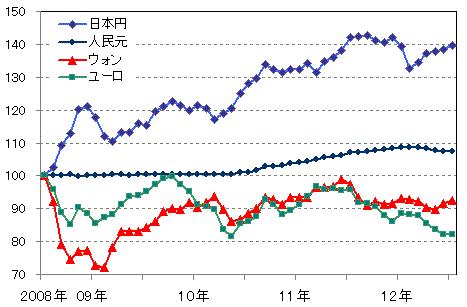| 三井物産戦略研究所WEBレポート 2012年9月14日アップ |
| 工業大国の行方 |
|
揺らぐ「工業大国」 日本の「工業大国」としての将来性に疑念が生じている。国内市場の飽和や、賃金、地代等の生産コストの上昇、そして円高の進行を受けて、多くの企業が国内での生産活動を維持できなくなってきているためだ。過去にも、そうした例は少なくない。産業革命で世界の工業化の先駆けとなった英国や、豊富な資源と巨大な市場の力で英国を凌駕していった米国でさえも、GDPに占める製造業のウェイトは1割程度まで低下し、工業大国の面影は既に過去のものとなっている(図表1)。
一般に製造業は、農業に比べて労働者一人当たりの生産性も所得水準も高いため、農業から製造業に労働力がシフトする「工業化」のプロセスは、経済全体の発展、それも国民の多くが参加し恩恵を享受できるタイプの発展に直結する。しかし、そのプロセスでは平均的な賃金水準や地価・地代等の生産コストの上昇が並行して進むため、国際競争力が低下し、製造業の成長にブレーキがかかるという展開がパターン化している。経済が発展した国の通貨は、為替市場において、物価の変動を除いた実質的な為替レートが上昇する傾向もある。こうした構図があるため、製造業を主力とする産業構造は持続し難いのである。 英国、米国の跡を継いだ「現役」の工業大国である日本、ドイツでも、2010年時点のGDP中の製造業比率は2割前後と、英国や米国、フランス等、他の先進諸国に比べると高水準であるが、1960年代の3割台後半の水準からは趨勢的に低下してきている。その傾向が今後も続くようであれば、工業大国としてのアイデンティティは揺らぐことになるだろう。 また新興勢力としては、米国を抜いて工業生産額世界一となった中国と、工業生産額は第7位ながら、製造業比率は30.5%と高所得国では突出して高い韓国の両国が典型的な工業大国と言える。台湾や香港、シンガポールなどとともに日本の後を追う形で工業化を遂げてきた韓国は、主力の自動車やエレクトロニクスが日本企業のシェアを奪う形で台頭してきたことに象徴されるように、製造業主導の経済発展の真只中にある。しかし、購買力平価(PPP)ベースの一人当たりGDPの水準は日本や欧州主要国のレベルにほぼ肩を並べており、生産コストの面では、既に追う側から追われる側に移行しつつある。新興国の代表格である中国も、産業構造の面では農業のウェイトが依然として高く、工業化の余地は大きいものの、工業化の進んだ沿海部を中心に、賃金をはじめとする生産コストの上昇ペースが加速してきている。中国のこれまでの経済発展において最大の武器であったコスト競争力は、低下に向かう可能性が生じている。 中国のコスト競争力の低下は、追われる側の日本やドイツ、韓国にとっては、工業大国路線に対する逆風を和らげる材料となる。しかし、中国の後にはインドやインドネシア、ベトナムといった次代の工業大国候補が数多く控えている。中国も含め、現役の工業大国が、製造業主導の経済を維持し続けることを目指したとしても、その道程は決して平坦なものではないだろう。 為替をめぐる明暗 現在の工業大国、日本、ドイツ、韓国、中国の4カ国は、相対的な生産コスト上昇という共通の課題を抱えている一方で、近年では、各国の通貨制度の違いと為替レートの変動によって、大きく明暗を分ける形になっている。2008年からの世界経済危機下では、財政・金融危機が深刻化したEUのユーロと、金融セクターが脆弱だと考えられていた韓国のウォンの対ドルレートは大幅に低下し、その後はやや戻したものの低位で推移している(図表2)。
この時期のユーロ安とウォン安については、両国の通貨政策も一因となっている。ドイツの場合には、ユーロ圏内に限れば為替変動がないうえに、共通通貨であるユーロの為替レートが圏内の他の国々の国際競争力や経済実態も反映して決まるため、圏内で最も競争力の強いドイツにとっては、圏外に対しても割安な為替レートになりやすい構造になっている。また韓国の場合は、2009年に経済危機からの回復局面に入って以降も、為替市場への介入によってウォン安を維持した。中国も、人民元の対ドルレートを介入によってコントロールすることで、為替の面での競争力低下を抑制してきた。 他方、金融セクターが相対的に安定していると評価された日本の円は、2005年以降の下落基調から急激に上昇に転じ、2009年以降も上昇基調が続いている。2010年9月には、介入によって急激な円高の回避を図ったが、この局面での円高は、それまでの過度な円安の修正という性格が強かったことに加えて、為替市場での円の取引規模がウォンや人民元よりもはるかに大きいため、円高を回避し続けることは不可能であった。円は、リーマンショック直前の水準と比べると、経済危機下の2009年初頭の段階では対ユーロでは約4割、対ウォンでは約6割切り上がった。その結果、ドイツと韓国が輸出主導で早期に回復基調を鮮明にしたのに対して、日本では、世界的な需要後退に円高が重なったことで輸出が急減した。それにともなって、日本経済は危機の震源となった米国や欧州諸国以上に落ち込むと同時に、国内での製造業の生産活動を維持できないのではないかという懸念が高まった。為替市場におけるドイツ、韓国と日本の対照は、それぞれの国の製造業の環境について、大きく明暗を分けることになったのである。 それぞれの将来像と工業大国の進化形 為替をめぐる明暗は、当面は続くことになるだろう。とくにドイツについては、ユーロの枠組みが崩れない限り、為替の面で競争力を削がれる可能性は抑えられる。そのためには、財政・金融危機に瀕しているユーロ加盟国の支援・救済や、財政面も含むユーロ圏の統合深化といった難題に取り組んでいく必要があるが、ユーロの枠組みを維持できれば、ドイツが「欧州の工場」の地位を保つことは難しくないだろう。 他方、中国や韓国の為替市場介入による自国通貨安誘導は、短期的にはともかく、長期にわたって続けることは不可能と考えられる。為替レートの決定は市場に委ねるのが原則とされていることに加えて、両国ともに、輸入物価の高騰を通じた所得の国外流出やインフレ圧力の高まりといった副作用が既に顕在化しているためだ。中国にとっては、現段階での最大の課題である消費主導の持続的な成長パターンへの転換に向けて、人民元の安定的な切り上げが有力な選択肢となっている。実際、2011年終盤になると、欧州危機の影響や国内景気の悪化を受けて、人民元とウォンにも下落圧力がかかりはじめたこともあって、中国、韓国ともに、自国通貨の価値を維持する方向の政策が見られるようになっている。 それを踏まえると、中国と韓国の課題は、レベルの違いはあるものの、いずれも製造業における産業構造の高度化ということになる。中国では、既に労働集約型の産業から資本集約型の産業への移行は進んでいるが、今後は、機械産業に代表されるような技術・知識集約型の産業を伸ばしていくことになるだろう。工業生産額に占める機械産業の割合は、日本、ドイツ、韓国がいずれも4割前後であるのに対して、中国はようやく3割に達した段階であり、ここを伸ばしていく余地は大きい。その方向に進めば、中国は、後続の追い上げはあっても、世界でも圧倒的な工業生産額を誇る、工業の「超大国」へと進化していくことになるだろう。 追う側の進化は追われる側にも進化を迫る。中国において技術・知識集約型の製造業が成長すれば、韓国や日本においては、同様の業種に一段と特化、集約していくことが大きな流れとなるだろう。そこでは、機械産業のなかでもとくに技術・知識集約的な分野に集中していくことに加えて、先端素材や医薬品、嗜好性の高い食品や衣料品など、幅広い領域が対象となる。そして、さらにその先を見据えると、生産プロセス自体は、工業超大国となる中国を含めて、コストの低い国外に移して、国内では商品企画やマザー工場における技術の開発・継承と生産プロセスの開発に特化していく流れも考えられる。 こうした流れは、製造業の高度化と評価することはできるが、付加価値生産額や雇用の面では、成長の鈍化、さらには縮小に向かう可能性が高い。現在の日本、そして将来の韓国が、規模や量の面で工業大国路線を維持することは、きわめて困難と言わざるを得ない。しかし、その将来像は、産業の主軸を製造業から金融やIT関連に移した英国や米国とは一線を画したものとなるだろう。 多くの有力な製造業企業が、経営・管理といった本社機能だけでなく、前述の商品企画や技術開発等、メーカーとしての中核機能を国内に維持しつつ、生産活動と市場とはグローバルに展開する。それによって、優れた技術や知識の基盤を次代に継承するとともに、新たな技術やアイディアを産み育て、それらを世界に送り出していく。GDP中の製造業比率は低下するが、個々のメーカーは世界を舞台に発展を続ける。これはいわば、工業の「母国」といったイメージで、グローバル化時代に適応した工業大国の進化形と位置付けられる。大国から母国への進化は、生産コストと為替の上昇に追い詰められつつある日本にとっては、「ものづくり」の面での優位性を維持、活用していくための、数少ない選択肢の一つと言えるだろう。 関連レポート ■国家間経済格差の縮小と産業の力 (三井物産戦略研究所WEBレポート 2014年2月17日アップ) ■世界経済の成長の構図−「新興国主導」の実相− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2012年12月18日アップ) ■「開国」の再定義−産業と文化のOutflowへの注目− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2011年6月14日アップ) ■東日本大震災後、日本経済はこうなる (チェーンストアエイジ 2011年6月1日号掲載) ■震災と向き合って−「復興後」をめぐる論点整理− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2011年4月15日アップ) ■円高と「通貨戦争」の現実 (三井物産戦略研究所WEBレポート 2010年12月15日アップ) ■日本の存在感−アイデンティティの再構築に向けて− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2010年10月12日アップ) ■経済成長の現実−成長鈍化と成長依存症の狭間で− (環境文明21会報 2010年10月号掲載) ■日本経済の「今」 (読売isペリジー 2008年10月発行号掲載) ■労働生産性から見る日本産業の現状 (The World Compass 2008年7-8月号掲載) ■日本産業の方向性−集中と拡散がうながす経済の活性化− (The World Compass 2008年2月号掲載) ■「成熟期」を迎えた日本経済 (セールスノート 2007年6月号掲載) ■「豊かさ」の方向性−浮かび上がる「消費者」ではないアプローチ− (読売ADリポートojo 2006年5月号掲載) ■日本経済「成熟期」の迎え方−新局面で求められる「常識」の転換− (読売ADリポートojo 2006年4月号掲載) ■「豊かさ」と「活力」と−成熟化経済と人口大国の行方− (The World Compass 2006年2月号掲載) ■再浮上した成熟化の問題 (The World Compass 2005年4月号掲載) ■経済の活力をどう確保するか−世界に広がる「貧困エンジン」のメカニズム− (読売ADリポートojo2003年12月号掲載) ■高齢化時代の日本経済 (The World Compass 2001年5月号掲載) |
||||||||
| Works総リスト |