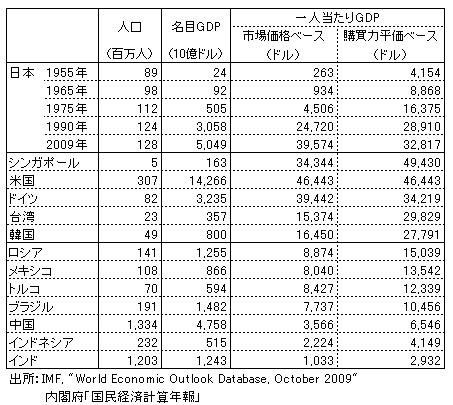| 三井物産戦略研究所WEBレポート 2010年3月8日アップ |
| 新興国経済の成長力 |
|
2010年、世界経済は2008年来の危機的な状況を脱し、本格的な回復に向けたプロセスを模索することになる。ただ、今回の経済の落ち込みは、通常の在庫調整や設備調整といった景気循環的な要因だけによるものではないため、世界各国で落ち込んだ耐久財消費や、住宅投資、設備投資が、早期に回復することは期待できない。さらに、サブプライムローンや証券化商品をはじめとして、前回の回復期から好況期にかけての金融ビジネスの活動が、経済危機を深刻かつ広範なものにしたとの反省が世界的に広く共有されていることから、それに類する金融的な手法によって、いわば「バブル的」に需要が回復に向かうことも考えにくい。そうした状況下、巨大なポテンシャルを有する新興国の経済への注目が一段と高まっている。 新興国の牽引力 2003年後半にスタートした前回の回復局面では、中国をはじめとする新興国以上に、住宅価格の上昇を追い風とした米国が世界経済を牽引した印象が強い。2003年当時、世界の名目GDPに占めるシェアは、米国の約30%に対して、中国は4.4%、インドは1.5%に過ぎなかった。その後、2006年までの3年間は、米国は年平均で3.1%、中国は10.7%、インドは9.0%のペースで成長し、世界経済の成長を牽引したわけだが、同期間の世界全体の年平均実質成長率3.8%に対するそれぞれの寄与度は、米国の0.86%に対して、中国は0.54%、インドは0.15%となっており、米国の寄与の大きさが顕著であった。 しかし、この間、さらには金融危機が生じてからも中国とインドの高成長は続いており、2009年時点での世界GDPに占めるシェアを見ると、米国が25%に低下する一方で、中国は8.3%、インドは2.2%にまで上昇している。したがって、2010年に、米国が3%成長に回復したとしても、中国やインドが10%成長を実現すると、それぞれの世界経済の成長への寄与度は、米国が0.75%にとどまるのに対して、中国は0.83%、インドは0.22%と、両国だけで1%を超える形となり、新興国が回復をリードする構図が鮮明になる。 こうした傾向は、中国やインドの高成長が続く限り、さらに鮮明になる。2020年までスパンを伸ばして、簡単な試算を行ってみよう。2020年まで中国とインドの両国が10%成長を続け、米国とその他の国の合計が、いずれも2.5%ペースの成長にとどまったとすると、両国の世界GDPに占めるシェアは、2020年時点で中国が16%、インドが4%にまで高まる。10%成長を前提にすると、両国だけで世界経済を年2%以上、成長させるパワーを持つことになる。一方、米国のシェアは22%に低下し、2.5%成長の場合、世界経済の成長への寄与度は0.6%程度にとどまる計算になる。そして、これらを前提とすると、2010年代終盤の世界全体の成長率は、2004年から2007年にかけての世界同時好況局面に匹敵する3%台後半にまで高まることになる。 これらは数字を仮置きした試算結果に過ぎないが、今後、中国とインドに代表される新興国の成長力への期待、あるいは依存が高まることは間違いないだろう。ただし、それは同時に、その成長が停滞する場合に、世界経済が受けるインパクトも年々大きくなってくるということでもある。 高成長の持続力 世界経済における新興国のプレゼンスが大きくなればなるほど、その高成長の持続力が問われることになる。実際、多くの新興国が、成長を続けていくうえでの弱点を抱えている。国によって濃淡はあるが、インフラの拡充や金融システムの整備、社会保障制度の確立など、克服すべき課題は少なくない。政治や社会の安定も重要なポイントとなる。しかし、これらの課題の克服が遅れることで経済の成長ペースが上がらなくても、それだけでその国の潜在的な成長性が失われるわけではない。新興国の成長力を決定的に失わせるのは、成長を阻害するファクターではなく、高成長の実現、維持に成功することで経済が成熟化の段階に入り、成長が限界を迎えてしまうことにある。 かつて日本にも、現在の新興国のように年10%ペースの成長を続けていた時代があった。戦後の復興期を抜けた1950年代半ばから1970年代初頭までの高度成長期である。1955年当時、日本の一人当たりGDPは9万5千円、物価水準を勘案して2009年時点のドルに換算すると4,154ドルに過ぎなかった(注参照)。この時期には、人々の衣・食・住の基礎的なニーズが未充足なまま残されており、企業にとっては「作れば売れる」状況であった。そうした状況下で、製造業を中心とする企業が急成長を遂げ、大量生産と大量消費を前提とした工業化と都市化が進行した。その結果、一人当たりGDPの値は、1967年に1万ドルを超え、1973年には1万6千ドル台に上昇したが、そこに至って、日本の高度成長には一気にブレーキが掛かった。直接的には、1971年のニクション・ショックによる為替の切り上げや1973年の石油ショックの影響が大きかったが、より根源的な要因としては、衣・食・住の基礎的なニーズが充足し、経済が成熟化の段階に入ったことが効いていた。「作れば売れる」状況は失われ、経済が成長するには、新しい商品・サービスの開発・投入や生産効率の向上による価格の引き下げといった企業側の努力によって、需要を創出していくことが必要になった。その結果、成長ペースは大幅に鈍化したのである。 こうした日本の経験と、現在の新興国の状況を対照してみると、物価水準の差を調整した購買力平価ベースの一人当たりGDPの水準は、ロシアやメキシコ、トルコ、ブラジルといった国々は、2009年時点でいずれも1万ドルを超え、既に日本の高度成長期終盤の水準に達している。その一方で、最大の注目株である中国は6,000ドル台、インドネシアが4,000ドル台と日本の高度成長期の序盤並みであり、3,000ドル弱のインドは日本で言えば高度成長期に入る以前の水準にとどまっている。今後、これらの国が10%成長を続けたとしても、日本の高度成長にブレーキが掛かった一人当たりGDP1万6千ドルの水準に達するのは、中国で2019年、インドネシアで2025年、インドが2029年という計算になる(人口については国連の2008年時点の中位推計における増加率を使用)。 もちろん、これだけで中国やインド、インドネシアの高成長がこのまま続くという結論は導けないが、当面は、これらの国が成熟化によって潜在的な成長力を喪失する懸念は小さいということは言えるだろう。これは、政治の安定や各種の制度的なインフラの整備といった条件付きであり、一時的に停滞する可能性も無視できないが、これらの新興国には、今後もしばらくの間は高成長を期待し得るということだ。 |
||||
注:購買力平価ベースの換算について ここでは、IMFが推計・公表している購買力平価(PPP=“Purchasing Power Parity”)ベースでドル換算したGDPの2009年の値を基点として、円建ての実質GDPの変化率を用いて過去の値を遡及、算出した値を用いている。なお、購買力平価ベースでの換算とは、各国通貨建ての統計データを他の通貨(米ドルを用いることが一般的)に換算する際に、市場の実勢レートを用いるのではなく、各国の物価水準から、各通貨が等しい購買力を有すると考えられる換算レートを理論的に算出し、そのレートで換算を行うことを意味する。 国際的な政策協調への期待 成熟化の問題がまだ先のことだとすると、新興国の経済成長の大きなネックとなるのは、やはり各種資源の供給不安と気候変動の問題ということになりそうだ。これらも、成熟化の問題と同様、新興国、とくに中国、インドの両人口大国の成長自体がもたらす問題という側面を持っているが、これらの問題は、新興国自身だけでなく、世界全体の経済活動を抑制するファクターとなる。既に、中国やインドでの将来の需要増を織り込むことで、2004年頃から各種の資源価格は高騰しはじめている。また、両国のCO2排出量の拡大を前提とした地球規模の気候変動の懸念は世界各国で共有されている。 新興国の成長が世界経済を牽引していくうえでは、中国とインドの両国が、各種資源、とくにCO2排出の原因となる化石燃料の利用効率を向上させることが必要不可欠な条件となるが、新興国の経済成長と、化石燃料の価格の安定が両立できれば、先進国にとっても大きなメリットになる。そのため、気候変動をめぐる国際的な議論では、新興国の化石燃料消費とCO2排出の抑制を先進国が資金的にも技術的にも支援していくことがコンセンサスとなっている。 とはいえ2009年12月のCOP15では、CO2排出抑制に向けた国際的な合意形成の難しさが改めて浮き彫りになった。また、資源と気候変動の問題に関してだけでなく、新興国の成長を資金面でサポートし得る国際金融システムや、自由貿易制度の整備など、さまざまな経済政策に関する国際協調の行方が、新興国経済の成長の可能性を大きく左右することになる。2010年は、グローバル化した経済を前提として国際協調を図る場としてのG20の首脳会議の定期開催がスタートする。そこでは、ここで挙げた問題についても、国家間での議論、交渉が進められることになる。その展開は、新興国の成長力を評価するうえでも、2010年の最大の注目点と言えるだろう。 関連レポート ■国家間経済格差の縮小と産業の力 (三井物産戦略研究所WEBレポート 2014年2月17日アップ) ■世界経済の成長の構図−「新興国主導」の実相− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2012年12月18日アップ) ■2010年代の世界の動きと産業の行方 (三井物産戦略研究所WEBレポート 2011年3月18日アップ) ■2010年の世界経済地図 (読売isペリジー 2010年4月発行号掲載) ■所得水準で見る新興国のマーケット (チェーンストアエイジ 2010年2月15日号掲載) ■2010年の世界経済展望−見えてきた金融危機後の世界− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2009年12月10日アップ) ■2009年の世界経済マップ−金融危機のインパクト− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2009年9月10日アップ) ■世界貿易の構造変化−グローバル化の潮流と金融危機− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2009年7月10日アップ) ■日本経済の「今」 (読売isペリジー 2008年10月発行号掲載) ■「成熟期」を迎えた日本経済 (セールスノート 2007年6月号掲載) ■日本経済「成熟期」の迎え方−新局面で求められる「常識」の転換− (読売ADリポートojo 2006年4月号掲載) ■「豊かさ」と「活力」と−成熟化経済と人口大国の行方− (The World Compass 2006年2月号掲載) ■再浮上した成熟化の問題 (The World Compass 2005年4月号掲載) ■「貧困の輸入」で活力を維持する米国の消費市場 (チェーンストアエイジ 2004年4月15日号掲載) ■経済の活力をどう確保するか−世界に広がる「貧困エンジン」のメカニズム− (読売ADリポートojo 2003年12月号掲載) |
||||
| Works総リスト |