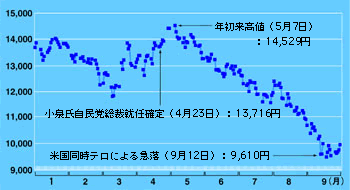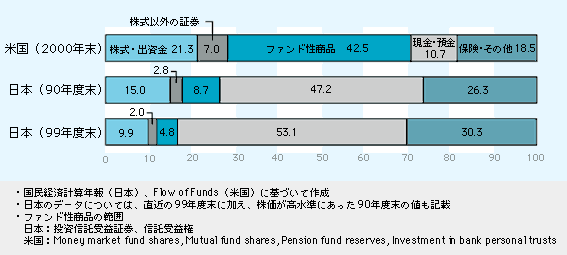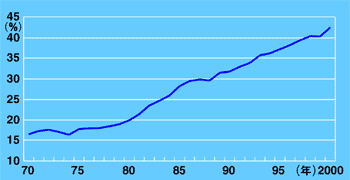| The World Compass(三井物産戦略研究所機関誌) 2001年10月号掲載 |
| 今求められる構造改革とは |
|
日本経済を再び活性化させるには構造改革しかない。これは、国民の大多数が認めるところでもある。構造改革が必要か否かは、もはや問題ではない。問題は、何をどう改革するのかにある。小泉政権の構造改革は正しい方向に向かっているのか。本稿では、今の日本にとって、どのような構造改革が必要なのか、問題の原点に立ち帰って考えてみたい。 危険をはらむ小泉改革 かつて橋本政権が推し進めた構造改革が97年からの大不況をもたらしたように、誤った構造改革は、効果があがらないだけでなく、状況をさらに悪化させることにもなりかねない。そうした懸念の高まりは、小泉政権成立以来の株価の低迷にも現れている(図表1)。 |
|||
|
|||
これまでの展開で見る限り、小泉改革は、橋本改革と同様の危険な要素をはらんでいる。それは、累増する銀行の不良債権の処理と財政赤字の削減とを、改革の直接の目標としている点だ。96年からの橋本改革は、景気が回復軌道に乗りつつあったのを機に、懸案となっていた財政赤字の削減、金融システムの健全化などを目指したものであった。しかし、財政赤字削減のために実施した消費税率や社会保障負担の引き上げは、回復しつつあった消費を一気に冷え込ませた。また、急速な体質改善を義務付けられた銀行は、財務体質強化のために、中小企業や個人商店への融資を減らさざるを得なくなった。いわゆる「貸し渋り」である。その結果、倒産する企業が続出したため、不良債権は減るどころか急増し、金融システムはかえって弱体化してしまった。 景気が上向いていた当時でさえ、方向性を誤った構造改革は極めて厳しい不況を招いた。不況下にある今、それと同じようなことをやれば、救い難い状況に陥る可能性が高い。小泉改革に対する最大の懸念は、「景気を犠牲にしても」という姿勢にある。「しばらくは痛みに耐えて」というと威勢良くはあるが、下手な治療では、痛いばかりで体が良くなることはない。 例えば、痛みの末に不良債権を処理できて、さらに公的資金の再注入によって銀行の自己資本を増強したとしても、銀行が投融資活動を活発化させる可能性は低い。バブル崩壊に起因する金融危機を経て、銀行は過度のリスクを取らないよう、金融当局、株式市場、そして預金者から厳しく監視されるようになったためだ。不良債権を処理した銀行が投融資活動を活発化させ、それが経済を回復させるというシナリオは、ほとんどあてにできないのである。 今必要なのは、日本経済の本当の病巣を明らかにし、病気の根本的な原因を断つことだ。もちろん不良債権や財政赤字の問題は解消されなければならないが、それは病気を治した結果として実現されるべきことであり、それ自体を改革の目的とするべきではない。 キーワードは「リスク」 それでは経済不振の根本的な原因とは何か。直接的な現象としては、まずは需要の低迷が挙げられる。個人消費と設備投資という需要の二本柱のいずれもが伸び悩んだため、企業収益は振るわず、税収も落ち込んだ。加えて、民間需要の不振を補うために財政支出を拡大し続けたため、財政赤字、そして政府の累積債務は急速に膨張した。また、需要の低迷に伴い、経営破綻に陥る企業が増え、銀行の不良債権が累増した。 ではなぜ需要は落ち込み、減税や金融緩和といった刺激策が効かないほどに低迷したのか。それを考えていくと、家計と企業いずれのセクターにおいても、「リスク」の問題に行き着く。 まず企業レベルでは、90年代に入って、情報技術をはじめとする技術環境の変化と経済のグローバル化の進行によって、多くの企業がビジネスモデルの根本的な変革を迫られた。またマクロの視点から見ても、産業構造の大幅な変化が避けられない状況となった。こうした変革期には、企業活動に伴うリスクの拡大は不可避である。ところが、バブル崩壊の影響をまともに受けた銀行には、その拡大したリスクを吸収することは不可能であった。そのため、既存企業の変革も、新しい企業の成長も阻害され、それに伴うはずの設備投資も低迷したのである。 一方、個人の生活のレベルでも、企業や産業の変革に伴い、将来の所得や、雇用そのものまでが不安定化した。加えて、そうした個人レベルのリスクを引き受けるべき社会保障の枠組みが、高齢化の進行によって一層弱体化し、悪くすれば崩壊する懸念が広まった。そうした状況下では、人々の消費意欲が盛り上がるはずもなかった。 このような企業、家計両セクターでのリスクの拡大と、それを処理する仕組みの欠如こそが、90年代の需要低迷の背景であり、今日の日本経済の病根と言うことができる。 構造改革の第一歩は行財政プロセスの改革 それでは、この病根を断つには、どうすれば良いのか。今打つべき手は、大きく分けて二つある。第一は、需要の低迷がこれ以上の悪循環に陥らないように、需要を下支えする政策だ。これは、病根を断つ大手術の前に、当面の出血を止める手立てととらえられる。需要の低迷がひとまず落ち着いて景気が底を打ちさえすれば、税収も増えて財政赤字の拡大にもブレーキを掛けやすくなるし、銀行の不良債権の拡大も抑えられる。 とはいっても、ただ単に需要拡大を目指して、財政支出を垂れ流したり、やみくもに銀行を支援するような政策では効果があがらない。それは、ここ10年の経験で既に明らかだ。景気刺激や銀行支援のために財政支出を拡大したり減税を実施したりすれば財政赤字が増え、それはいずれ増税の形で返ってくることが、だれにでも予想できる。それが人々の将来に向けての不安を増大させ、消費にしろ投資にしろ、経済活動を委縮させてしまうのである。 将来への不安感を増大させることなく、現在の需要拡大を実現する政策としては、現在の支出拡大と将来の支出削減をセットにした財政政策が有力だと考えられる。ただし、単に全体の支出額や赤字額を公約や法制化の形で約束するだけでは、必要な公共サービスの削減にもつながりかねず、将来の不安はぬぐえない。あくまでも現在の支出プロジェクトそのものが、将来の支出削減、あるいは収入拡大に直結するものでなくてはならない。例えば、将来確実に必要になると考えられるプロジェクトを前倒しで実行することが考えられる。高齢化社会に向けた生活インフラのバリアフリー化や、情報技術の一層の発展をにらんだ情報通信インフラの強化などは将来間違いなく必要になる。それを今からやっておくことは、将来の支出拡大を防ぐことになる。 また、民間企業が現状の体力不足と将来への不安感から踏み切れないでいる事業を、民間への売却を前提に、国営事業として立ち上げることも考えられる。そこでは、ベンチャー・キャピタル的な投資事業や介護事業などが候補になるだろう。前述のインフラ整備を、独立した国営事業として実行することもできる。いずれにしても、きっちりした事業性の把握と、将来の日本の生活環境、ビジネス環境を改善できるプロジェクトであることが必要だ。 さらに、こうした手法を、例えば高速道路の整備・運営や郵便事業など既存の国の事業に適用し、民営化を前提に、バランスシートの作成など、独立した事業体としての整理を進めておけば、それらの事業を株式会社化し株式を公開することで得られる資金を国債の償還にあてることが期待できるようになり、累積財政債務に対する人々の不安の解消につながるだろう。 しかし、これらの政策は、これまでの常識や従来の財政ルールに縛られていたのでは実現できない。官僚機構に組み込まれた暗黙のルールも含めて、財政政策を決める政治・行政のプロセスを大幅に変更することが前提となる。突き詰めると、経済再建のための第一歩は、政治改革や行政改革、それも単なる省庁再編や公務員数削減といった見かけだけの改革ではなく、行財政プロセスそのものの改革なのである。 経済再建のカギは新しいリスク処理の枠組みの構築 需要の下支えと並行して打つべき第二の政策は、拡大するリスクを処理する社会的な枠組みの整備である。これが、現在の日本が抱える病巣を根本的に治療するための方策ということになる。そして、そのカギを握るのが、経済におけるリスク処理の主役ともいえる金融システムおよび金融ビジネスである。とはいえ、不良債権処理や公的資金による資本注入によって銀行の体力を回復させただけでは、リスク処理の枠組みとしては十分とはいえない。従来の日本型金融システムでは、拡大を続けるリスクを処理することはできないからだ。 従来の日本型金融システムの性格は、米国のシステムと対比すると理解しやすい。米国のシステムは、国民一人ひとりが各自の状況に応じてリスクを取れるようにすることで、社会全体のリスク許容力を最大化しようというものだ。そのために、個々の企業のリスクとリターンを小口化した「株式」に加え、投資信託や年金など、個々のリスク(および、それにともなうリターン)を切り分け、また組み合わせて組成した多種多様なファンド性の金融商品が用意されている(図表2)。 |
|||
|
|||
それに対して日本の金融システムは、国民一人ひとりでリスクを取るのではなく、社会全体でリスクを処理するスタイルを取っている。システムの中核である銀行は、事実上リスクのない「預金」の形で人々から資金を集め、銀行がリスクを取って融資や投資を行う。銀行がリスクに耐えられるのは、運用資産が巨大で多くの企業に分散して投資できるためと、「護送船団方式」と称された手厚い規制に守られていたためだ。 国民一人ひとりがリスクを取れるだけの資産を持っていなかった敗戦直後の日本の急速な経済復興と、その後の高度成長に際しては、日本型の金融システムは強力な武器になった。しかし、このシステムは、経済全体が明確な目標に向かって突っ走っていける時代には適しているが、先行きが不透明な時代に、慎重に手探りで進んでいくのには向いていない。それは、個人がリスクを取らないシステムは、経済活動におけるリスクに対する認識を薄れさせ、責任の所在をあいまいにするという弊害を持っているためだ。 その弊害は、80年代後半以降、極めて深刻な形で顕在化した。リスクへの認識の甘さは、銀行の不動産関連融資の急拡大と、その結果としてのバブルの膨張をもたらし、その崩壊によって、日本経済はリスクを取る力をほとんど失ってしまった。そして、その状態からいまだに立ち直れないのは、責任の所在があいまいで、最終的な処理ができずにいるためでもある。 日本経済再生のためには、金融システムの再建は不可欠の条件である。とはいえ、既に時代にそぐわなくなっていた従来の日本型金融システムを復活させても仕方がない。今望まれるのは、一人ひとりが相応のリスクと責任を取れるような、新しい金融システムの構築である。 ファンドを主体とした金融システムへ 新しい金融システムの構築のためには、税制面での優遇措置などで、個人の株式取得を促すことも一つの方策である。預金中心から株式中心へ、あるいは間接金融から直接金融へ、という考え方も広まってきている。しかし、それだけでは十分ではない。リスクの大きさや性格を異にする金融商品、特に、株式よりも小口投資が可能でリスクの小さいファンド性の金融商品を多彩に品ぞろえすることで、個人の潜在的なリスク許容力をフルに顕在化させることが必要だ。 個人にとっても、適度なリスクを取ることで長期的に高い投資収益を得ることができれば、自らの将来への備えを手厚くできる。あるいは、預金の場合に比べて、年ごとの貯蓄額を小さくしても、同じだけの資産を形成することが可能になる。預金性商品からファンド性商品へと資産をシフトさせることは、個人レベルの将来に対する不安の緩和、場合によっては貯蓄性向の低下、すなわち消費性向の向上にもつながるわけだ。 ファンド性の金融商品と、その基盤となる投資ファンドの成長は、規制緩和を受けて競争が激化する金融ビジネスにおいて、各金融機関が顧客の確保と収益性の向上を目指す動きを原動力として進むものと考えられる。99年に始まった銀行による投信販売はその端緒であり、2002年に予定されるペイオフ凍結解除も、預金商品からファンド性商品への移行の追い風となるだろう。ファンド主体の金融システムでは、金融ビジネスの事業領域は大きく広がる。ファンドの組成、運営はもちろん、既存企業の財務・経営サポート、投資を前提とした有望企業の発掘と育成、そして、多様化する金融商品をコーディネイトして個人に販売するリテール分野。これらの事業領域では、既存の金融機関のみならず、企業サポートではコンサルティング・ファームやベンチャー・キャピタル、総合商社、リテール分野では新設のネット企業などもライバルとなる。もちろん、外資系金融機関との競合も想定される。 その延長線上では、郵便貯金をどうするかが、極めて大きな問題になる。ペイオフ凍結解除によって銀行預金にもリスクが生じることを前提にすると、最もリスクが小さく流動性が高い金融商品の提供主体としての郵貯は、国民にとって、これまで以上に重要な存在となる。解体・民営化が望ましいとする議論もあるが、国の補償によるリスクフリーの預金性商品を提供させる一方で、新たに設立されるファンドに資金を供給し、その立ち上がりをサポートさせるということも考えられるだろう。 また、投資ファンドの成長は、全般的な企業価値の向上につながる可能性がある。米国でファンドへの資金移動が顕著に進んだのは80年代に入ってからであるが(図表3)、それは「株式の死」とまでいわれた70年代の株価低迷を脱却する要因となった。ファンドは大株主として企業の経営を厳しく監視し、企業価値の向上を追求する。零細な個人株主の場合と違って、単なる監視ではなく、役員の人選や経営戦略の選定、さらには経営者の交代など、直接的に経営を左右することもできる。それが企業経営に緊張感を与え、企業活動の効率化、企業価値の向上が実現された。加えて、M&Aによって企業価値の最大化を目指す動きも、ファンドが基点になることで活発化した。これらの流れが、90年代の米国の全般的な株価上昇をもたらしたのである。同様の効果は、日本においても十分期待できる。 |
|||
|
|||
岐路に立つ小泉改革 ファンド主体の金融システムへの移行にどれだけメリットがあっても、また金融ビジネスがどれだけそれを志向しても、株式市場が低迷を続けている現在のような状況では、預金からファンドへの資金移動など、進むはずがない。金融システムの刷新には株価の底入れが前提となる。その意味で、前に述べた、将来の不安を打ち消すような財政拡大策、そして、それを可能にする行財政プロセスの改革こそが、今の日本の最優先課題と位置付けられるのである。 行財政プロセスの改革は、さまざまな既得権益を否定することにほかならない。日本では、大多数の人が、仕事や日々の暮らしのなかで、何らかの形で既得権益に依存している。それが「雇用」という形をとっていることもある。そして、それを失うことによる不利益こそが、構造改革にともなう「痛み」である。当然、だれもが均等にその「痛み」を味わうわけではない。失う既得権益の大きい人、否定される行財政プロセスの近くにいる人ほど、「痛み」が大きくなる。 その最たる存在が政治家であり官僚である。だからこそ、行財政プロセスの改革を志向する政治家が登場し、しかも政権を担うようなことは、ほとんど期待できなかったのである。その意味で、小泉首相の存在と小泉政権の成立は、一種の奇跡ととらえられる。 小泉政権による構造改革の提案を見ると、メリハリを利かせた財政支出、国営事業の民営化促進、特殊法人の見直しなど、本稿で示した構造改革の方向性とオーバーラップする政策が数多く含まれている。そして、それらのかなりの部分が、小泉政権でなければ議論にもならなかった政策だ。それだけに、小泉政権が倒れるようなことになると、その損失は計り知れない。そうなる前に、不良債権や財政赤字といった表層的な問題に拘泥することをやめ、改革の方向性を転換することが望まれる。 米国での同時多発テロの影響もあって株価は急落、日経平均で1万円を大幅に割り込んだ。それは、小泉改革の危険な一面をより鮮明に浮かび上がらせることにもなったが、同時に、改革の方向性を転換する機会が与えられたと考えることもできる。小泉政権が、非常事態ともいえるこの機をとらえ、改革の方向性を転換できるか否か。日本経済は今、大きな岐路に立っている。 関連レポート ■小泉改革を考える−復興と改革と摩擦の4年間− (読売ADリポートojo 2005年10月号掲載) ■これからの景気回復−モザイク型景気拡大の時代へ− (読売ADリポートojo 2004年12月号掲載) ■2004年への期待−不安の時代から問題を直視する時代へ− (読売ADリポートojo 2004年1-2月号掲載) ■不良債権の悪循環−求められる新しい金融ビジネスの構築− (読売ADリポートojo2003年7-8月号掲載) ■「不安」の時代−目指すべきはリスクに立ち向かえる社会− (読売ADリポートojo2003年5月号掲載) ■都市とインフラ−インフラ整備をどうするか− (読売ADリポートojo 2002年4月号掲載) ■新時代の金融システム−「良い構造改革」の先に飛躍の可能性− (読売ADリポートojo2001年11月号掲載) ■リスクと金融システム−日本型金融システムの限界− (読売ADリポートojo2001年10月号掲載) ■不良債権問題をどう考えるか−本質はリスク処理システムの再構築− (読売ADリポートojo2001年8月号掲載) ■小泉改革への期待−良い構造改革、悪い構造改革− (読売ADリポートojo2001年7月号掲載) ■銀行の将来像−そこに未来はあるか− (読売ADリポートojo2000年6月号掲載) |
|||
| Works総リスト |