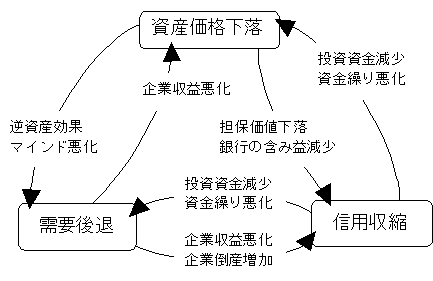| 学士会会報2003年3号(5月発行)掲載 |
| 日本経済再建への突破口 |
|
「失われた10年」という言葉が流行ったのは、世紀の変わり目を迎えた2、3年前のことだ。しかし、21世紀に入っても日本経済は低迷を続け、「失われた」年月は10年では終わらないことが明らかになると、この言葉を目にすることもなくなってきた。 思えば1989年に大学を出て以来、大半をいわゆる民間エコノミストとして過ごした私の社会人生活は、その大部分が「失われた」年月に入っている。その間、仕事のうえでは客観的な立場というか、やや他人事のように日本経済の動向を見てきたわけだが、個人的にも、勤めていた銀行が経営破綻に陥り新たな職場を探さざるを得なくなるという、それなりに深刻な事態も経験した。 そうしたなかで、日本経済はどうなっていくのか、どうしていくべきなのか、といった問題は、常に私の意識のなかにあった。ここでは、仕事のレポートとは異なる、縦書きの文章を書く機会をいただいたことでもあり、データの裏付けが十分でない仮説も含めて、これまでに考えてきたことを述べてみたい。 「失われた10年」のメカニズム 今となっては、バブル崩壊後の不況が、普通の不況、すなわち単なる需要後退ではなかったことは明らかだ。需要後退に資産価格下落、信用収縮を加えた三つのシュリンク(縮小)現象が相互に原因となり結果となることで増幅しあい、スパイラル的に進行していくきわめて困難な状況だったのである。これは、「トリプル・スパイラル」とでも呼べる構造だ(下図参照)。 |
||
|
||
資産価格の下落は、消費意欲、投資意欲を冷え込ませ、需要の後退をもたらす。加えて、多数の銀行が、不動産を担保としていた融資の焦げ付きと株式の含み益の減少で自己資本に癒しがたい傷を負い、貸出を拡大する力を弱めていく。また、需要後退は、企業収益の悪化などを通じて、資産価格下落と信用収縮を一段と加速させる。そして、銀行の貸し出しの圧縮、すなわち信用収縮は、資金面での制約をきつくすることで、さらなる需要後退と資産価格下落をもたらす。これらの悪循環が連鎖的に続いていく。 このメカニズムは、今でこそ鮮明になっているが、経済の停滞が長期化、深刻化していく途上では、必ずしもクリアに認識されてはいなかった。そのため、政府も民間のエコノミストも事態を楽観しがちで、経済政策は常に後手に回り、事態を深刻化させる結果になったのである。 順を追ってみていくと、まずは発端となった資産価格下落の影響を軽視してしまった。ピークからの下落幅は、93年までの間に、株、土地とも約500兆円、合計で1,000兆円近くにも達した。これは、当時のGDP(国内総生産)の約2倍に相当する額である。ところが当初は、それが深刻な需要後退をもたらすという認識は薄く、バブル期の風潮を反省しようという気分もあって、むしろ資産価格下落を歓迎する向きさえあった。むろん現実はそう甘くはなく、資産価格の下落は消費意欲、投資意欲を冷え込ませ、需要は一気に後退に転じたのである。 それを受けて、政府は91年の後半には財政支出の拡大、金融緩和といった景気拡大策を本格化させ、95年頃には景気は上昇に転じた。ここで二つ目の大きな判断ミスが出た。水面下で積みあがっていた銀行の不良債権の影響を見落としたまま財政再建を優先して、消費税率の引き上げをはじめ、財政を引き締める政策を採ってしまったのである。その結果、脆弱だった回復の芽は摘まれ、景気は再び悪化していった。 それにともなって深刻さを増した信用収縮の脅威は、一般企業だけでなく、資産価格下落で傷を負った金融機関にも襲いかかり、97年11月には大手金融機関が相次いで破綻した。不安を募らせた人々は預金の引き出しに走り、その結果、多くの金融機関が資金不足を恐れて急速に貸出を圧縮したため、金融システム全体が機能停止寸前の状態となった。その急場は、ペイオフを凍結し預金の全額保護を確約することで、なんとか切り抜けることができたが、その後もさらに多くの企業、金融機関が破綻の憂き目をみることとなった。 第四のスパイラルと構造改革の危険性 「失われた10年」を抜けて2000年に入ると、ITブームで一時的に回復期待が盛り上がった時期もあったが、それも米国における、いわゆる「ITバブル」の崩壊とともにしぼんでしまった。それを受けて、小泉政権による構造改革の時代を迎えたわけだが、ここでも、事態を楽観し過ぎている懸念が拭えない。 小泉政権の経済政策は、従来型の財政拡大や金融緩和では経済を活性化できないという前提に立って、一旦落ちるところまで落ちて禍根を断ってから、経済を再起動するという考え方を基本としている。具体的には、当初掲げていた財政赤字削減や、銀行の不良債権処理の加速がそうだ。そして、落ちていく過程では、国民は「痛みに耐える」ことを要求される。 これは一見すると日本経済の現状を相当深刻に捉えているように見える。しかしこの路線は、落ちるところまで落ちれば「底」があることを暗黙の前提としている。先に示したトリプル・スパイラルのメカニズムを前提にすると、不良債権処理によって需要後退、資産価格下落が進めば、それが新たな不良債権を生むという悪循環で、どこまで落ちても底がないという事態は十分予想できる。その意味で、底の存在を前提とした小泉政権の改革路線に対しては、事態を甘く見ているのではないかという懸念が拭えないのである。 さらに、経済の停滞が長期化するのにつれて、人々の将来に対する不安感が高まってきている点も見逃せない。長引く停滞で醸成された不安感は、人々の消費活動を萎縮させ、それが企業の投資活動を後ろ向きにさせる。その結果、経済の停滞は一段と深刻化し、それが人々の不安感をさらに高めるという悪循環、いわば「不安と不況のスパイラル」だ。 「痛みに耐える」ことを要求する小泉改革は、人々の不安感を煽り続けている。トリプル・スパイラルに加えて第四の悪循環が起動している現状を考えると、この路線はあまりにも危険な賭けと言えるのではないだろうか。 三つのターゲット では、どうするか。財政支出を垂れ流したり、やみくもに銀行を支援するような政策では効果はあがらない。それは「失われた10年」の経験で既に明らかだ。景気刺激や銀行支援のために財政支出を拡大したり減税を実施したりすれば財政赤字が増え、それはいずれ増税の形で返ってくることが予想される。そのため人々は将来に不安を抱き、消費にしろ投資にしろ、経済活動を萎縮させてしまう。 今求められているのは、人々の間で高まっている不安感を軽減すること、あるいは社会の持つ「不安を処理する機能」を強化することで、経済活動を活発化させていく施策である。財政赤字や銀行の不良債権といった表面的な問題の解消は、その結果として付いてくるもの、という捉え方が大切だ。 「不安への対処」ということで見渡してみると、突破口としては「教育」「自治」「金融」の三つの領域が浮かび上がってくる。 第一には、「教育」の領域において、人々の「自分自身への投資」、すなわち仕事につながる技術や知識の修得を促していくことが考えられる。社会や経済の不安定さが増し続けている現在、将来に備えて専門性や技能を身に付けたいという思いは、少なくとも潜在的には強まっているはずだ。それは子供にも大人たちにもあてはまる。そうした思いに応えられる有意義な教習プログラムを提供できれば、人々の不安の軽減につながるとともに、「自分自身への投資」という潜在的なニーズを需要として顕在化させることにもなる。 専門性や技能を修得するための教習プログラムの提供では、大学に加えて各種の専門学校の役割が拡大する可能性も高いし、まったく新しい参入者が活躍することも期待できる。既成の大学や学校の枠組みを超えた新しいエネルギーの注入がカギを握るだろう。対象となる分野は、IT関連のさまざまな技能、製造現場での諸技術、デザイン、金融工学、情報探索、マーケティング等々、無数にある。 これらの教習プログラムが人々の「自分自身への投資」の対象となるには、それらが人材を使う企業の側のニーズを反映したものであることが前提となる。同時に、職業教育のシステムが、一般の教養教育のシステムと効果的に結びつくこと、加えて、既に社会に出て働いている人々の再教育の枠組みを整えていくことも必要だ。 第二には「自治」の領域において、パブリック・ニーズを顕在化させ、新たな事業を興していくために、公共セクターの力を活用していくことが考えられる。一般の民間企業は、経済が低迷するなか、リスクの大きな事業を展開する余力をなくしている。それに対して、政府や自治体が行う公共事業は、人々から税金の形で強制的に集めた資金を使うので、リスクの小さい事業としてスタートさせることができる。しかし、民間の企業と違って競争がないために非効率になったり、現実のニーズに合わない事業になったりしやすいという問題が指摘されている。加えて、国も地方も財政赤字が累増しており、公共事業の拡大は望みにくい状況だ。 そこで、事業主体として初期投資を行いサービスを提供するのは民間の企業やNPOとし、政府や自治体はその利用者としての国民、地域住民を代表して、事業主体にサービス提供を委託する事業モデルが登場してきた。税金で費用をまかなうことで事業のリスクを抑えながら、民間のノウハウと資金を活用しようというわけだ。PFI(Private Finance Initiative)の手法もその一種である。そうした新しい形式の官民分業による事業展開は、現時点では試行段階にとどまっているが、成功事例が出はじめれば、新規事業の展開も、それにともなう投資も、急速に拡大する可能性がある。 第三には、経済活動にともなうリスク処理の主役である金融システムの再構築がやはり重要になる。とはいえ、高度成長のために最適であった銀行中心の金融システムは過去の遺物であり、完全に機能を失っている。現時点で必要なのは、銀行の再建ではなく、新時代に適応できるまったく新しい金融システムの構築である。 そのモデルは、投信や年金といったファンド型の金融業態を主役とした米国の金融システムに求められる。米国において金融システムが経済の中心として有効に働きはじめたのは、投信や年金が家計資産の中核となった80年代後半以降のことだ。ファンド型業態は、いわゆる間接金融と直接金融の中間的な性格を持っている。金融資産の価格変動をはじめとするリスクは個々の投資家が負担する一方、ファンドの運営主体は、投資先に関する情報の収集・分析を担うとともに、主要株主あるいは大口債権者として投資先企業を監視する機能も果たしている。80年代に入ってこのスタイルが主役となったことで、米国の金融システムは、経済活動におけるリスクを社会的に処理する枠組みとして、また企業活動を制御する枠組みとして機能しはじめたのである。日本の金融システムの再起動、ひいては日本経済の再起動のカギは、銀行主役からファンド主役への移行にある。 おわりに 本稿では、経済再建に向けた突破口として、「教育」「自治」「金融」の三つの領域に焦点をあてた。そこで想定している施策は、いずれの領域においても、その枠組みの根本的な変革につながるものである。 その変革の方向性は、単に現在の経済不振の突破口というだけでなく、生活水準が高度化した一方で高齢化にともなう経済成長の鈍化が予想されるこれからの日本経済にとって、20年、30年のタームで必要なものでもある。しかし、複雑な利害関係や変化を厭う勢力が障害となって、それを実行に移すことは、容易なことではない。それが、10年を超えてさらに悪化しようという経済危機を契機に動き出すのであれば、「失われた」年月の歴史的な意味合いにも、少しはポジティブな要素が加わることになるだろう。 以上、仮説を多分に交え、誤謬を恐れず書き連ねてきたが、今後はより正確な現状分析と具体的な施策を提示するための調査を進めていきたいと考えている。本稿は、その出発点となる考え方を述べさせていただいたものであるが、皆様のご批判、ご叱正をいただければ幸いである。 関連レポート ■未来のための貯蓄と投資−これからの焦点は人材の育成に− (読売ADリポートojo 2005年4月号掲載) ■これからの景気回復−モザイク型景気拡大の時代へ− (読売ADリポートojo 2004年12月号掲載) ■不安の時代の若者たち (GYROS 2004年11月刊行 第8号掲載) ■時代が求める新たなサクセスモデル (国民生活金融公庫調査月報 2004年7月号掲載) ■2004年への期待−不安の時代から問題を直視する時代へ− (読売ADリポートojo 2004年1-2月号掲載) ■経済再建のカギは「教育」にあり (The World Compass 2003年3月号掲載) ■「官」と「民」との役割分担−「官」の役割は受益者としての国民代表へ− (読売ADリポートojo 2002年10月号掲載) ■リスクと金融システム−日本型金融システムの限界− (読売ADリポートojo 2001年10月号掲載) |
||
| Works総リスト |