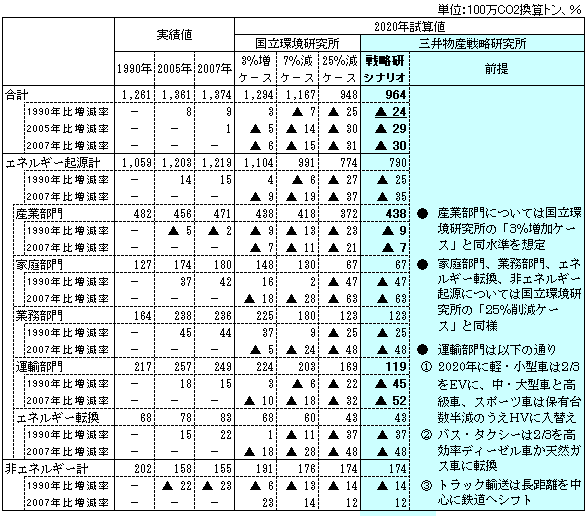| 三井物産戦略研究所WEBレポート 2009年12月15日アップ |
| 「CO2排出25%削減」達成のシナリオ−「低炭素化」で経済・産業を活性化させるために− |
|
世界の経済発展を加速させたグローバル化の進展 2009年の世界経済は、前年来の金融危機からの脱却を最大のテーマとして回ってきた。そこで主役を担ったのは世界各国政府による各種の政策対応であったが、そのなかでも目立ったのが、「グリーン・ニューディール」という言葉に象徴される積極的な環境対策を景気刺激策と融合させる政策展開であった。そして、その流れを受けた年後半には、ポスト京都議定書の枠組み構築に向けた議論が高まってきた。そうしたなか、日本の民主党が打ち出したのが、CO2排出量を1990年比25%削減するというきわめて野心的な目標であった。この目標は、当初は選挙に向けたアピールの色彩が強かったが、8月末の総選挙で政権交代が実現したことで、これからの日本の経済、産業を左右するきわめて重要な意味を持ってきた。25%削減は可能なのか。それを目指すことで日本経済はどうなるのか。ここではこれらの論点を、根本のところから整理してみたい。 低炭素化の四つの方策 「経済が縮小する」、「企業の国際競争力が低下する」、野心的なCO2排出目標に対しては、こうした懸念が寄せられている。そもそも不可能だとの見方も根強い。確かに、低炭素化を進めれば、経済活動を抑制したり、日本企業の操業コストを押し上げたりといったネガティブな影響が出てくる可能性はある。しかし、それは低炭素化の方策次第と言える。一国の低炭素化には大きく分けて四つの方策が考えられるが、そのなかには、経済や企業の活動を萎縮させる方策がある一方で、経済を活性化させ成長を加速させる方策もあるからだ。それらの関係をまとめると、以下のようになる。 方策1:経済活動の抑制 低炭素化の方策として、第一に考えられるのは、各種の規制や課税の強化によって、単純にすべての経済活動の水準を低下させることだ。これは当然、経済を縮小させ、個人の所得、消費も、企業の売り上げも収益も縮小することになるわけで、最も望ましくない方策と言える。 方策2:低炭素型の産業構造への転換 第二の方策は、産業の構造転換による低炭素化だ。経済の全体の規模は維持しつつも、鉄鋼や化学などCO2排出量が多い産業を縮小し、かわりにCO2排出量の少ない情報創造型のコンテンツ産業などにウェイトを移していくことでも低炭素化は進められる。そのための具体的な施策としては、企業のCO2排出に対する規制や課税の強化によって、CO2排出量が多い産業活動を抑制することや、排出量取引によって低炭素型産業を補助することが考えられる。この方策は、全体としての経済規模にはニュートラルな方策であり、単純に経済活動全体を縮小させるよりは望ましいと言える。しかし、規制や課税の分、企業のコストは上昇し、国際的な競争力は削がれることになる。さらに、その結果として鉄鋼などの生産が、エネルギー効率が低く生産量当たりのCO2排出量が大きい国にシフトする可能性が高い。そうなると日本の低炭素化は進んでも世界全体として見れば、CO2排出量はむしろ増加することにもなりかねない。この方策も、第一の方策よりは良いとしても、やはり望ましいとは言えないだろう。 方策3:低炭素型のライフスタイルへの転換 第三に考えられるのは、人々のライフスタイルの転換による低炭素化である。たとえば、自家用車で旅行に行くかわりに、自宅での読書や音楽鑑賞、ゲームなどで余暇を過ごすようになればCO2の排出は抑えられる。買い物の際の包装の簡素化やエコバッグの利用、リサイクルの徹底など、その範囲はきわめて幅広い。既に導入されているクールビズの試みも、この方策の一つと位置付けられる。実際にこれを実現するための施策としては、電気料金の引き上げのように消費者の損得勘定に訴えるほか、メディア等での情報発信による人々の省エネ意識の醸成や、低炭素化に向けたムーブメントの演出が考えられる。この方策は経済や産業へのプラスの影響もマイナスの影響も大きくはない。選択肢に入れておくべき方策と位置付けられる。 方策4:低炭素型の商品・技術の導入 第四の方策は、生産活動、消費活動の双方に、エネルギー効率の高い機器や技術を導入していくことである。さまざまな商品、サービスの生産に高効率の設備や省エネ技術を導入していくことや、従来型の自動車、家電、住宅を、エコカーやエコ家電、省エネ住宅に置き換えていくことで、CO2の排出を抑えていこうという方向性だ。火力発電を太陽光、風力等の再生可能エネルギーや原子力に置き換えていくことも、この方策に含まれる。それを促すための具体策は、他の方策の場合と同様、規制と課税、補助金の組み合わせによって、企業や消費者のアクションを引き出していくことが想定される。 この方策では、低炭素型の機器や設備の生産・供給やインフラの建設が前提となる。そのためのコストは、何らかの形で国民が負担することになるが、その支出は最終的には誰かの所得となるため、負担と所得の増加分は相殺される。また、恒常的な需要不足の状態にある日本においては、機器や設備、インフラの需要拡大は、ほぼストレートに経済全体としての生産拡大、さらには企業収益と個人所得、雇用の拡大につながることが想定される。それは経済の活性化と企業の経営環境の改善、国民の生活の安定をもたらすものであり、低炭素化に向けてはこの方策が最も望ましいと言えるだろう。ただし、規制や課税によって産業セクターに設備導入を強制する施策を採ると、第二の方策と同様に産業の海外流出を促すことにもなりかねず、その点には注意が必要である。 別枠:国外からの排出枠の購入 国際公約の達成という意味では、上記のような国内での排出削減策のほかに、国外から排出枠を購入する手もある。排出枠を市場で取引する仕組み自体は、取引に参加できる経済主体に排出削減のインセンティブを生じさせるため、低炭素化を進めるためのきわめて有力なツールと考えられる。しかし、一国の経済が削減目標達成のために排出枠を購入するとなると、その購入費用は国外への所得移転となり、その分は需要と生産を縮小させることになる。第一の方策に比べると経済活動へのマイナスの波及効果は限定的だと考えられるが、やはり積極的に採るべき策とは言い難い。ただ、今後の国際的な交渉の推移によっては、新興国の排出削減に対する技術的、資金的な支援もカウントできるようになる可能性もある。その場合には、日本製の設備、機器の輸出や日本企業の事業展開につながることも考えられるため、単なる排出枠購入に比べてメリットがあるものと考えられる。 25%削減のシナリオ 前項で整理したCO2排出削減の方策を踏まえて考えると、2020年時点で1990年比25%削減という目標を実現するための望ましいシナリオとしては、前項の第三、第四の方策で可能な限り削減し、それで不足する部分は産業の国外流出が生じない範囲で第二の方策を用い、それでも足りない最後の不足分は国外からの排出枠の購入で賄うというシナリオが想定できる。 これを部門別に整理すると、結果的に第二の方策につながりかねない産業部門(主として製造業)への規制や課税の強化はできる限り避け、これまで低炭素化への対応が遅れてきた家庭部門と業務部門(サービス産業やオフィスなど)、運輸部門に含まれる自家用車の部分を中心に、第三、第四の方策を用いて、行動様式の転換と低炭素型の機器の導入を加速させるシナリオが想定される。 このシナリオでどこまでCO2排出を削減できるのか、簡単な試算を行ってみよう。試算のベースには、国立環境研究所が2009年3月に発表した資料「AIM/Enduse[Japan]による2020年排出削減に関する検討」で提示し、その後のCO2排出削減に関する各種の議論で叩き台となってきた試算結果を用いる。 国立環境研究所の試算では、対応策の強度と削減幅によって複数のシナリオが提示されている。図表1には、そのうちの、経団連が2009年5月に提示していた1990年比4%増に近い「1990年比3%増加(2005年比5%削減)ケース」と、前の自民党政権が掲げた2005年比15%削減に近い「1990年比7%削減(2005年比14%削減)ケース」、現在の民主党政権が掲げている目標に相当する「1990年比25%削減(2005年比30%削減)ケース」の、三つの試算結果を載せている。
この資料では、こうした試算結果から「対策技術の普及を推し進めるとともに、活動量に影響を与えるほどの炭素の価格付けを適切に組み合わせることによって1990 年比25%削減することも可能」との結論を提示している。しかし、そこで示された25%削減のケースでは、既に低炭素化を進めてきた製造業を中心とする産業部門に対しても、1990年比23%、2007年比でも21%という大幅な削減を求めることになる。日本の製造業は、1970年代の石油危機や1980年代の急激な円高の際などに、厳しい省エネ目標やコスト削減目標を達成してきた実績はあるが、企業活動のグローバル化が進んだ今日において、日本の製造業が厳しい条件に挑んでまで国内での生産を維持するとは限らない。25%削減を図るうえで、製造業に過度の期待をかけることは、危険な賭けと言わざるを得ない。 そこで、いささか極端ではあるが、産業部門に求める削減幅は「3%増加ケース」の水準(1990年比9%、2007年比7%)にとどめ、その分、他の部門での削減に期待するシナリオを考えてみたい。とはいえ、国立環境研究所の試算の前提を見る限り、家庭や業務、エネルギー転換、非エネルギー起源の各部門に、25%削減ケース以上の削減を求めることは難しそうだ。唯一、切り込む余地がありそうなのは、2007年時点で日本の総CO2排出量の18%を占める運輸部門、とくに同9%の自家用乗用車の部分である。 国立環境研究所の試算では、25%削減のケースでも、CO2排出量がガソリン車比で70%のハイブリッド車(HV)への転換が中心だが、ここでは、よりドラスティックなシナリオとして、ガソリン車比30%(現在の日本の電源構成の場合)の電気自動車(EV)への転換を急速に進めるケースを考えてみた。具体的には、極端な仮定ではあるが、2020年時点で軽・小型車の3分の2がEV(販売ベースでは100%がEV)に、中・大型車と高級車、スポーツ車は保有台数半減のうえ全数がHVに転換しているほか、バスやタクシーなどでは高効率ディーゼル車や天然ガス車への転換が進むなどの前提を置くと、2020年時点の運輸部門のCO2排出量は1990年比45%の削減が可能という結果が導ける。国立環境研究所の25%削減ケースに、ここでの運輸部門の試算結果を含めると、産業部門を3%増加ケースにとどめても、全体では1990年比24%削減となる(図表1の戦略研シナリオ)。この試算はラフなものであり厳密な話はできないが、排出枠の購入や他国の低炭素化支援によって埋める必要があるのは数%分で済むということである。 この試算に含まれる国立環境研究所の25%削減ケースには、家庭部門では高断熱住宅の普及率100%(2008年30%)や住宅用太陽光発電設備の普及910万戸(2005年26万戸)、業務部門では高断熱建築物の普及率100%(2008年40%)、発電所では太陽光発電の発電量450億KWh(2005年3億KWh)、風力発電が200億KWh(2005年19億KWh)といった野心的な前提が置かれている。これらの導入が想定ほどには進まない場合は、前項で第二の方策として挙げた人々のライフスタイルの転換がどこまで進むかがポイントとなる。またEVに関しては、一般的には2020年になっても国内販売の数%程度にとどまると見られており、それを踏まえると、全体の6割弱の小型車に限るとはいえ、販売ベースで100%にまで普及が進むという前提は、常識的には不可能と言えるほど困難であることは間違いない。 しかし、その不可能に挑んでいかない限りは、前項で整理した第一、第二の方策、すなわち経済の縮小や産業の国外流出を抜きにCO2排出25%削減は達成できそうにない。それに対して、急速なEV化を実現できれば、産業の国外流出は回避しながら25%削減という目標に近づくことができる。EVをはじめとする低炭素型の商品の導入を急速に進めるための費用は必要だが、前述のとおり、それは大部分が、国内産業の生産拡大、さらには雇用や所得の拡大につながるものであり、経済はむしろ拡大、活性化する。CO2削減策が、いわゆる「成長戦略」にもなり得るわけだ。加えて、世界的な戦略産業である環境関連産業が、世界に先駆けて実用化・量産化の段階に入り、世界の低炭素化を主導する体勢が整うことにもなる。ここでの試算の前提にした水準は無理だとしても、常識外のペースでのEV化と家庭部門での排出削減を極限まで進めることは、25%という目標の達成に向けて、有力な選択肢と言えるだろう。 求められる政治のリーダーシップ 家庭部門、とくに自家用乗用車のEV化に主眼をおいたCO2排出削減を進めるためには、規制と課税、補助金を組み合わせて、消費者にEVと低炭素型の家電、住宅への更新や家庭用太陽光発電設備の導入を促すことが基本となる。 家電や住宅、太陽光発電設備については、電力料金の大幅な引き上げによって消費者のインセンティブを高める施策が考えられるが、人々の生活への影響が大きく、反発が広がる可能性が高いことに加えて、ガソリン車からEVへの転換のインセンティブを削いでしまうと考えられるため、選択し難い。これらについては、トップランナー制度のような、エネルギー効率が低い商品の販売や使用を制限する規制の強化と、補助金の投入によって普及を促す施策が主力となるだろう。2010年までの短期間で供給量を急拡大させることを前提にして、早期に量産効果を出すことができれば、製品や素材・部材の価格低下が見込まれ、緩やかに需要を拡大するケースに比べて補助金総額は少なくて済むことも期待できる。 EVの普及に向けては、ガソリン車の販売・保有への課税強化、EVの購入・生産への補助金投入、ガソリンの生産・販売への課税強化などによって、消費者にEVへの転換のインセンティブを与えることが考えられる。ただ、2010年時点では車両自体の供給体制も充電設備などのインフラも、ほとんど整っていない。産業セクターにそれらへの投資を実行させるためには、彼らにEVの急速な需要拡大を確信させるだけのドラスティックな施策が必要になる。とはいえ、極端な施策には財政的な負担や人々の反発が予想される。 そこで、たとえば目標年次直前の2019年にガソリン価格を5倍とか10倍に引き上げるといった制度変更を早期に宣言し、消費者と企業に、準備する期間を与える手法が考えられる。ガソリン価格の大幅な上昇を前提に、消費者は、2019年までにEVに乗り換えるか、自動車の保有自体をやめるかを選択する。メーカーは消費者の動きを前提に供給体制を急ピッチで整え、政府や官民の連携組織が充電インフラの整備を進める。そのための費用は全体で5兆円程度と見込まれるが、政策的な投融資や保障によって、その調達を支援する施策も有効だろう。 EVの購入に対する補助金は、ガソリン車との価格差に対して提供していくことが想定されるが、家電等の場合と同様、需要の急拡大を前提にコスト面での量産効果を早期に引き出せれば、緩やかに普及が進む場合に比べて、補助金の総額は限定的なものにとどまるだろう。また、EVへの転換により、自動車産業は事業構造の大幅な見直しを強いられるし、自動車部品のメーカーや石油精製、ガソリンスタンドといった業種は大きな打撃を被ることになる。それらの産業に対しては、EV化で必要になる事業への転換支援を含めて、各種の手当てを行う必要がある。 これらの施策はあまりにもドラスティックで、経済や産業セクター全体にはメリットが大きいとしても、打撃を受ける一部の産業はもちろん、変化と負担を嫌う消費者からも反発される可能性が高い。それを突破するうえでは、政権担当者には一時の国民感情に流されない強力な意思とリーダーシップが求められる。さらに、将来のガソリン価格上昇を前提として企業や消費者の対応を引き出すには、その施策が確実に履行されることを企業や個人に確信させることが必要である。政権交代を実現したばかりで、次の総選挙での再交代の可能性も意識せざるを得ない現在の政権にとっては、きわめて厳しいハードルと言えるだろう。 EV化を主眼とするCO2排出削減目標の達成は、経済や産業の活性化だけでなく、化石燃料の消費抑制によるエネルギー安全保障の実現、外交における発言力の向上、自動車由来の大気汚染の解消といったメリットも想定できる。また、EV化を契機に都市内、都市間の交通体系を見直すことになれば、より安全な交通システムへの転換や、生活者のための都市インフラの再構築につながることも期待できる。ハードルは高いが、得るものはさらに大きい。それを実現していくには、政権、政党の枠組みを超え、産業セクターとも密に連携してきめ細かい政策を立案していくことが求められる。現政権の、将来を見据えた構想力と果断な判断、実行力に期待したい。 関連レポート ■震災と向き合って−「復興後」をめぐる論点整理− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2011年4月15日アップ) ■2010年代の世界の動きと産業の行方 (三井物産戦略研究所WEBレポート 2011年3月18日アップ) ■2010年の世界経済展望−見えてきた金融危機後の世界− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2009年12月10日アップ) ■気候変動問題と「低炭素化」の潮流 (読売isペリジー 2009年10月発行号掲載) ■低炭素化のリアリティ−資源と環境、二つの難題への共通解− (The World Compass 2008年9月号掲載) ■変質した環境問題−企業の力をどう活用するかが焦点に− (読売ADリポートojo 2004年10月号掲載) ■経済発展と自然環境−二者択一からの脱却− (読売ADリポートojo 2001年2月号掲載) |
|||||
| Works総リスト |