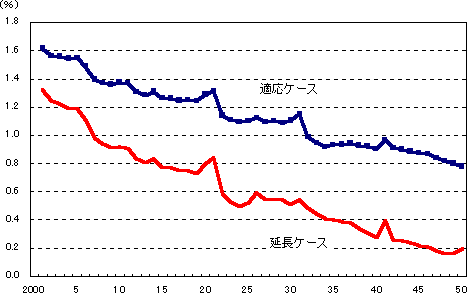| The World Compass(三井物産戦略研究所機関誌) 2001年5月号掲載 |
| 高齢化時代の日本経済 補論2:前提を変えた試算(1)−成長率は維持できないか− |
|
第一に、高齢者の生産活動への参加が拡大するケースが考えられる。今後は年金、医療などの社会保障の縮小により、高齢者が仕事を続けるインセンティブが高まることが予想される。また、消費市場でも高齢者の割合が高まることから、高齢者向けのサービス提供など、高齢者の就労機会が拡大する可能性もある。ここでは、2050年までの間に、60歳以上の層の労働力率が、1999年時点の一段階若い層と同じ水準(具体的には、60〜64歳の層は1999年の55〜59歳並み、65〜74歳は同60〜64歳並み、75〜84歳は同65〜74歳並み)にまで向上するケースを想定する。 第二に、女性の生産活動への参加が拡大するケースも想定できる。これからは、産業の情報化、情報の産業化に伴って、時間や場所を選ばない仕事が増える結果、女性が子育てをしながらでも、生産活動に参加する余地が広がることが予想される。女性の生産活動への参加が拡大すると、少子化を一段と加速させたり、家庭での教育が劣化するといった問題が生じる可能性もあり、一概に肯定的にとらえることはできない。とはいえ、その是非を問うことは本稿の問題意識から外れるので、ここではその問題はひとまず度外視して、試算を行うことにしたい。子育ての年代(20代後半と30代)以外では、各年齢層の女性の労働力率が2050年までの間に男性と同じ水準にまで上昇し、子育ての年代では、各年齢層の男女の労働力率の格差が2050年までに半分になるケースを想定する。 以上のような想定で試算を行った結果が下図4の「適応ケース」である(補論1の前提で求めた試算結果を延長ケースとして併せて記載している)。この図によれば、成長率は2010年代後半には1.3%、2040年代後半には0.8%程度と、低下幅は相当程度抑えられるものの、80年代以前のレベルは維持できないという結論になる。 試算の枠組みだけでいえば、投資比率の上昇、資本ストックの除却率の低下、労働生産性に対する資本装備率の弾性値の上昇など、成長率を維持するシナリオを描けないわけではない。しかし、現状から判断する限り、そうした変化が起こる理由は特になく、現時点では、成長力の低下は避けがたいと考えるのが妥当であろう。 |
|||
■本論「高齢化時代の日本経済」へ |
|||
| Works総リスト |