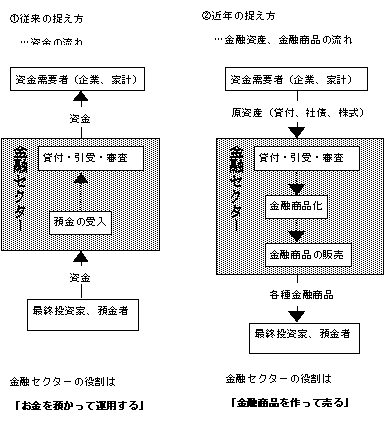| 近代セールス 2001年2月1日号掲載 |
| IYバンク誕生のインパクト(インタビュー) |
|
この1月にもスタートが予定されるイトーヨーカ堂のIYバンク。なぜ、流通業は金融業務進出を目指したのか、その背景や既存業界との競合の行方などについて、いま改めて三井物産戦略研究所の小村智宏・主任研究員に聞いた。 ――小村さんは著書「流通業の金融ビジネス参入」(中央経済社刊)の中で、「コンビニを傘下に持つ大手流通業による預金性商品に特化した形での参入」を仮説として立てられました。これは、イトーヨーカ堂銀行、すなわちIYバンクの設立の実現で、いま、現実のものになろうとしています。 改めて伺いますが、IYバンクの設立にはどんな評価をお持ちですか。 小村 流通業が金融ビジネスを目指したのには、いくつかの環境要因があります。IYバンクの設立の意味を考えるには、この点から見ていかなくてはなりません。 これには二つの側面があると思います。ひとつは金融サイドの変化、もうひとつは流通業サイドの変化です。 まず、金融サイドの変化からお話ししましょう。皆さんは既にご存知のことだと思いますが、金融ビッグバンの始動は、いわゆる「護送船団方式」の崩壊が前提になっています。護送船団方式とは、具体的には、厳しい参入規制、業務規制や金利規制によって、金融機関が安定的な利益を上げられる状況を維持する、事実上のカルテルだったと言っていいでしょう。 このカルテルは、高度成長経済の終焉、債券市場の成長、金融の国際化といった流れを受けて弱体化していましたが、これがバブルの崩壊によって致命的な打撃を受けました。 こうして、金融ビックバンは、機能を失った護送船団方式と名実ともに訣別し、次代の金融システムの枠組みや原則を構築する作業としてスタートを切りました。その目指すところは、規制緩和のよって金融ビジネスにおいても様々な創意工夫が活かされる環境を整備することにあります。 もちろん、そこでは既存の銀行や証券会社だけでなく、他産業の企業、あるいは全くの新設企業であっても、それぞれの能力とアイディアを生かした金融ビジネスの展開が可能になるはずだと思います。実際、そうなったわけですけれどね。 ――護送船団方式の崩壊は、実力や体力のない金融機関が容赦なく淘汰される、そういう状況も創出するわけですね。 小村 そうです。護送船団の時代には、個別の銀行の経営が破綻した場合でも、その資産・負債は他の健全銀行が引き継ぐことが暗黙の前提としてあり、預金者にツケが回されることはあり得なかった。だからこそ、一般消費者は金融機関の経営状態や安全性を気にすることなく、預金を預けることができたわけです。 こうした枠組みは、護送船団方式が崩壊した後も、いわゆるペイオフ凍結の措置によって継続されています。その意味では、来年4月のペイオフ解禁こそが、護送船団方式と訣別し、本格的なビッグバンの時代に入っていく最大の節目になると思います。 銀行預金とは、安全性が売り物の金融商品です。決済手段として使われるのも、安全性があってこそです。しかし、ペイオフが解禁されると、その安全性が大幅に低下することになります。そうなると、預金という商品は国が保証する郵便貯金や、リスクとリターンの関係が明確な投資信託などの商品と競合することは、今以上に困難になる。また、銀行間の比較で、消費者が不安だと考えた銀行から健全とみられる有力銀行へ資金がシフトする動きも出てくるかもしれません。 こうした流動的な時代は、新たなモデルで金融ビジネスを展開しようとする側にとっては、大きなチャンスということもできるわけです。 ――流通業サイドの変化要因としては、どういうものが上げられますか。 小村 90年代以降の規制緩和を背景とする、競争の本格化がまずあげられると思います。流通業界にとっての90年代は、金融業界と同様、惨憺たる10年間でした。ヤオハンや長崎屋の倒産、相次ぐ百貨店の閉店、直近ではそごうの破綻と、暗い話題には事欠きません。しかし、流通業は、価格競争一辺倒の消耗戦を抜け出す道を模索はじめたのです。 流通業の消耗戦脱出に向けた戦略は、大きく二つに分化しつつあります。第一は「専門性の強化」。 それと対極をなす第二の戦略は、「ワンストップショッピング」の追求です。 特に、後者は、衣料品を中心に食品、雑貨、家具、家電など、幅広い商品を扱う百貨店や総合量販店(GMS)、あるいは、24時間営業で若者の生活に最低限必要な商品を揃えたコンビニ、これらの業態は、いずれも、一つの店で一度に買い物を済ませられる「ワンストップショッピング」の利便性で、顧客を惹きつけてきました。それをさらに強化しようという方向にいまあります。 また、GMSやコンビニの品揃えの幅は、既に「商品」の範疇にとどまってはいません。GMSでは、自社店舗を中核とするショッピングセンター(SC)に映画館やレストラン、アミューズメント施設、スポーツ施設などを組み込む動きが盛んです。コンビニでは、DPEやクリーニングの集配、宅配便の受付け、予約したチケットの発行など、「サービス」のメニューも、随分と広がってきています。 金融ビジネスへの参入は、このワンストップショッピングの追求という流れの一環と位置づけられるわけです。つまり、新たな収益源としての位置づけと同時に、自社店舗の集客力を高めることが、大きな狙いとなっているということです。 ――流通業の金融ビジネス参入の戦略について、もう少し具体的にお聞かせください。 小村 流通業の金融ビジネス参入が、自社店舗の競争力強化を主目的とするものであれば、必ずしも自らが金融ビジネスを手掛ける必要はないわけです。大規模なGMSやSCでは、集客力向上のために、他社が運営する専門店やアミューズメント施設を迎え入れることは普通に行われていることです。 コンビニのサービス提供も、コンビニ自体は窓口となるだけで、DPEやクリーニングなどの実際のサービスは専門の業者が担当するケースが多いと思います。 金融ビジネスの場合も、大型店舗ではインストア・ブランチ、コンビニではATMの設置といった形で、金融機関と連携した事業展開が、第一歩でした。強力な流通業との連携は、金融機関にとっても大きなメリットとなります。流通業と連携した金融機関は、潜在的な顧客が多数集まる場所に、低コストで営業拠点を構築することができるからです。 しかし、そのためには、金融機関の超えるべきハードルは大きい。流通業サイドの狙いが、顧客の満足度、店舗の集客力の向上にある以上、提供する金融サービスにも相応のレベルが求められるからです。営業日や営業時間をとっても、週末に来店客が集中する商業施設の中で、金融機関のインストア・ブランチだけが店を閉めていては逆効果でしかない。平日にしても、そこだけ3時で閉店というわけにはいかないのです。 コンビニに設置するATMも、コンビニという業態の特性を考えれば、24時間とは言わないまでも、相当な長時間稼動が求められます。当然、その間のメンテナンスやセキュリティ確保の体制も、流通サイドとの連携の中で構築していくことになります。 この段階で、既存金融機関が、店舗の競争力強化を図る流通業の期待に応えられないということになると、流通業自らが金融ビジネスを展開するというシナリオが見えてくるわけです。現実性が高いのは、本業の物販との関係が深い代金決済に関連する分野。この分野では、カード事業や消費者金融事業は従来から行っています。 英国のスーパーマーケット銀行のように、決済のベースとなる預金性の金融商品を自前で提供することも考えられます。しかし、そうなった場合は、既存金融機関と流通業は、競合関係に入ることになるということです。 ――IYバンクの設立は、そうした流れに沿ったものということですか。 小村 そう思います。イトーヨーカ堂は99年4月、自社の全店舗へインストア・ブランチを導入する計画を発表しましたが、その半年後の11月には自ら銀行を設立する計画を明らかにしました。これは、交渉した金融機関の対応が不満であったためだろうと思われます。まさに、先程述べたシナリオ通りの展開ということです。 ただ、私の予想と違ったのは、「銀行」の設立を図った点です。イトーヨーカ堂が提供しようとしている決済機能は、必ずしも銀行でなくても可能な事業です。現に、トヨタ自動車は、証券会社の資格で決済業務を行う計画を打ち出しています。 それなのに、なぜ銀行なのか。認可の手続きは面倒だし、設立後も様々な規制に縛られることにもなる。そうした犠牲を払ってまでイトーヨーカ堂が手に入れようとしているのは、「安全・確実」の代名詞としての「銀行」というブランドなのかもしれません。 しかし、バブルの崩壊や金融不祥事を経て、消費者が今でもそうした幻想を持っているのかどうかは大いに疑問は残ります。 ――IYバンクの強みは、どんなところにあると思われますか。 小村 流通業が自ら金融ビジネスに乗り出す際、最大の武器となるのは、顧客が足を運んでくれる店舗網です。イトーヨーカ堂の場合、主力の大型店舗が約180店、グループのコンビニ、セブン・イレブンが約8,200店。しかもそれらの店舗網は、高度な情報網、物流網でネットワーク化されています。 加えて、コスト競争力の面でも圧倒的に優位にある。人材にしろ店舗にしろ、金融機関の経営資源は、流通業に比べてはるかに高コストです。もちろん、そうでなくては提供できない高度なサービスもあるでしょう。しかし、比較的単純な商品、サービスに限定すれば、流通業の低コストの経営資源を活用して低価格で提供することは十分可能です。 また、流通業にとっての決済関連ビジネスのメリットは、顧客情報収集に利用できる点が見逃せないところです。カード事業と預金性商品の提供を組み合わせると、顧客の購買活動を把握するために最適なツールとなるからです。 大手流通業では突出して収益性の高いイトーヨーカ堂も、近年は成長性、収益性の両面で壁に突き当たっている感が強い。そうした状況下で、顧客情報の分析、活用に突破口を求めたとしても不思議はないという気がします。 顧客情報の活用に本業の浮沈を懸けるということになると、流通業にとって、決済関連の金融ビジネスは、ある程度採算を度外視しても取り組む価値のあるビジネスということになります。そうなると、ただでさえコスト競争力に劣る既存の金融機関が対抗するのは、一層難しくなるでしょうね。 ――流通業の参入を迎えて、消費者向け金融ビジネスの領域での競合は、今後どのように展開するのでしょうか。登場するのは、既存金融機関とイトーヨーカ堂グループに代表される大手流通企業、さらに、ここにきて急速にクローズアップされてきたネット企業ということになりそうですが。 小村 新規参入組のアドバンテージはコスト競争力です。既存金融機関のように高コストの経営資源(店舗、人員など)に縛られていない点に優位性があるでしょう。流通企業の方は、それに強力な店舗網が加わるわけです。 一方のネット企業の方は、最新の技術、インフラを前提に、一からビジネスモデルを組み立てられるというメリットを持っています。インターネットという新しいコミュニケーションツールの活用によって、専門性を有した人材が少なくても、相応のサービスを低コストで提供することもできるでしょう。 その意味で、一昨年春の時点では、株式や保険商品のディスカウントブローカーのスタイルで価格競争を仕掛けていく戦略がもっとも有力だろうと考えていました。しかし、実際には、少額取引に限定した決済サービスを提供しようという「eBANK」構想のように、きわめて斬新かつ有望なビジネスモデルも提起されているわけです。 対する既存金融機関のアドバンテージは、金融の専門性を有した人材を多数確保していることにあります。それを最大限に活かせる新しい業態へ進化しない限り、新規参入組に対抗して生き残っていくことは難しいのではないでしょうか。 ――既存金融機関としては、どんなスタイルの営業形態が今後、有望だとお考えですか。 小村 最も有力な業態は、様々な金融商品を同一の店舗で扱うスタイルでしょう。 従来は、預金なら銀行、株なら証券会社、保険商品なら保険会社と、別々のチャネルでしか購入できなかった。それを一つの店舗にまとめて顧客の利便性を向上させたビジネス。これは、食料品のカテゴリーでいえば食品スーパー、住関連商品でいえばホームセンターに相当するもの、流通用語風にいえば、金融専門スーパーです。 各種の専門スーパーは、顧客の生活の一場面に焦点をあてて、そこで必要な商品、サービスをまとめて提供する業態、言い換えれば、特定の範疇で専門性とワンストップ性をバランスさせた業態ということができます。 この路線は、既に銀行を中心に、既存金融機関の戦略に組み込まれています。銀行員は、投資信託の販売開始を契機に、「預金を集める」という意識から「様々な金融商品を販売する」という意識にシフトしつつある(下図)。当然、提供するのは自社商品には限りません。顧客の幅広いニーズを満たすための多様な商品の供給元を確保するため、グループ内の連携を強化したり、新たに国内外の金融機関との提携関係を構築したりという動きが既に活発化しているのは、ご承知の通りです。 規制緩和のスピードとの兼ね合いはあるものの、既存金融機関の進化は、このワンストップ型の業態に向かう可能性が高いと思います。 |
||
|
||
――今後、登場してくるであろう金融スーパーと、流通業やネット企業による金融ビジネスの関係の帰趨は、どうなりそうですか。 小村 これは、いささか予想し難いですね。 預金性商品の供給を含む決済関連ビジネスでの「競合」はもちろん考えられますが、商品分野で棲み分けることができれば、インストア・ブランチやATMの相互接続による「連携」も再び視野に入ってくるでしょう。さらに、顧客情報の活用の仕方次第では、より密接な関係を築く「融合」に進むことも考えられなくもありません。 ただ、展開がどれだけ複雑でも、突き詰めれば、「いかに顧客のニーズを発掘し、それを満たしていくか」という極めてシンプルな大原則に行きつくわけです。 金融界の多くが長い間忘れていた、その大原則に立ち戻ることが、新時代への適応の第一歩となるだろうという気がします。 |
||
| Works総リスト |